こだわりアカデミー
形も行動も、珍妙奇妙な謎の生物、変形菌。 生物界でも、ちょっとはみ出し者的存在なんです。
生物界のはみだし者−変形菌
国立科学博物館植物研究部主任研究官
萩原 博光 氏
はぎわら ひろみつ

1945年、群馬県生れ。北海道大学農学部農業生物学科卒業後、国立科学博物館に勤務。農学博士。 専門は変形菌分類学、特に細胞性粘菌。著書に「森の魔術師たち−変形菌の華麗な世界」(83年、 共著、朝日新聞社)、「南方熊楠の図鑑」(91年、共著、青弓社)、「日本変形菌類図鑑」(95年、 共著、平凡社−写真下−)等がある。
1996年1月号掲載
異星生物が出現!と、アメリカで大騒ぎに
── ところで、変形体がアメーバのように動き回るというのは、どんなふうに動くんですか。
萩原 変形体の移動は、時速数cmと極めてゆっくりのスピードなので、肉眼では動いているようには見えないほどです。扇形に広がって、バクテリア、カビ等の餌に向かって進んでいきます。
|
|
萩原 手のひらサイズのものをよくみかけますが、直径50cmくらいのものも決して稀ではありません。1m以上に広がった変形体を見たこともあります。変形体の大きさは、種類によって限界が決まっているようです。
また、変形体はナイフで2つに切ればそれぞれが独立して2つになりますし、同じ種類の変形体同士がくっるいて一つになってしまうこともあります。
── どの程度の距離を移動するんでしょうか。
萩原 移動の最終的な目的は胞子を風で飛ばすことですから、より高いところで子実体をるくろうとします。そのため草や木、石や岩の上などに這い上がっていく場合もあり、数m移動するものもいます。
実はそれで、ひとつ面白いエピソードがあるんです。「ススホコリ」という変形菌が1973年春に北アメリカで起した有名な事件です。その年は例年になく湿度が高かったため、変形体が大発生しまして、子実体をつくる場所を求めて電柱などに上がっていったんです。鮮黄色の大きな塊があちらこちらに出現し、しかも、どうも動いているらしいと分かったため、異星生物が地球を征服に来たなどというデマも飛び交うほどの騒ぎになり、住民を恐怖に陥れたんです(笑)。
── 確かに、こんな生物が地球上にいるなんてあまり知られていませんから、本当に怖かったと思います。
ところで、変形菌は動物の仲間なんでしょうか、植物の仲間なんでしょうか。
萩原 現在、生物世界は、生き物としての分類という点では、動物界、植物界、菌界、プロチスタ界、モネラ界の5界に分類されています。その中で変形菌は、単細胞生物であるという点で動物界・植物界に属さず、運動能力を持つという点でキノコやカビ等の菌類の仲間には入れず、また細胞核を持つ真核生物であるという点で、バクテリアや藍藻等の原核生物で構成されるモネラ界にも入れないということで、結局、プロチスタ界に入れられてしまいました。プロチスタ界というのは、単細胞生物で構成されていまして、運動能力のある生物も、葉緑素を持つ生物も含まれているという、系統的にはちょっと雑多なグループなんです。つまり、他の界からはみ出した生物のたまり場みたいなところへ入れられてしまったというわけです。しかし、このプロチスタ界でも、変形菌はちょっと異端者的存在でして、近い生物がいないんです。言ってみれば、生物界のはみ出し者というわけです。そういう意味では、異星生物みたいなもんですね(笑)。
 |
| 萩原氏の研究室は同博物館筑波実験植物園にある (写真は同施設内にあるサバンナ温室) |
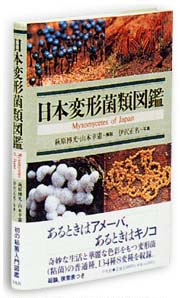 |
| 萩原氏の著書『日本変形菌類図鑑』(平凡社)。 表紙左上のキノコ状の子実体が「ルリホコリ」、右上「スミスムラサキホコリ」、左下「タマツノホコリ」、右下「エリタテフクロホコリ」 |
1997年12月6日−98年2月8日、東京・上野の国立科学博物館で企画展『変形菌の世界』を開催。 99年11月22日−2000年1月31日、栃木県立博物館(宇都宮)にてテーマ展『変形菌-菊地理一生誕100年記念』開催予定。 2000年7月20日−8月27日、仙台市立博物館において開催される生物特別展で変形菌が特別展示される予定。98年11月に東洋書林から出版された『図説 日本の変形菌』(山本幸憲著;日本の変形菌研究の第一人者)は、既知の日本産変形菌全種が掲載されており、興味のある方にはお薦めの書、とのこと。2015年、第25回南方熊楠特別賞受賞。
 サイト内検索
サイト内検索





