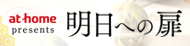こだわりアカデミー
抗生物質が効かない細菌(耐性菌)が出てきました。 しかもそれはどんどん増大しています。
抗生物質が効かなくなる−耐性菌の恐怖
日本歯科大学微生物学教室教授
吉川 昌之介 氏
よしかわ しょうのすけ

1934年大阪生れ。59年、東京大学医学部医学科卒業、64年、同大学院生物学研究科博士課程修了(細菌学専攻) 。東大医科学研究所入所。助手、助教授を経て82年より教授(細菌研究部長)。95年より現職。専攻は細菌学、 分子遺伝学。主な編著書に「細菌の病原性−その分子遺伝学」(84年、丸善)、「遺伝子からみた細菌の病原性」 (89年、菜根出版)、「医科細菌学」(89年、南江堂、95年改訂)、「細菌の逆襲」(95年、中公新書)、等がある。日本細菌学会評議委員、日本感染症学会会員。
1995年9月号掲載
細菌感染症は実は減少していない
──細菌感染症、俗に伝染病と言われる病気は、人類の科学の力ですでに克服したと思っていましたが、先生の著書「細菌の逆襲」を拝読しますと、必ずしもそうとは言い切れないようですね。
吉川 確かに抗生物質ができてから、一般の人はもちろん、医者までもが、細菌感染症は完全に治せると考えるようになりました。それは例えば日本など医療先進国では、少なくとも当初は事実だったわけで、伝染病はほとんどなくなりました。しかし、近年になって、なんと細菌が抗生物質に対する耐性能力を持つようになってきたんです。つまり抗生物質が効かなくなるという状況が出てきたのです。
一方、グローバルに見ますと、発展途上国を中心に、細菌感染症は依然猛威を振るっているというのも現実です。例えば、コレラはここにきて記録破りと言っていいくらいの患者数が出ていますし、結核も感染者数は一世紀前よりも今の方が多いんです。
──地球規模で見れば、なくなるどころか、むしろ増加しているんですね。
ところで、抗生物質が効かなくなってきたというのはどういうことですか。
吉川 おおきくわけて2つの要因があります。
まず一つめは、細菌が持っている染色体の変化によるものです。
そもそも細菌というものにも、生きていくために必要な仕組みというものがあります。この仕組みの設計図とも言うべき遺伝情報が細菌の染色体の上に乗っているわけで、その仕組みを壊すのが、本来の抗生物質の役割なんです。ところが、細菌が遺伝情報を変えてしまうため、それまでの抗生物質では歯が立たなくなるんです。
──遺伝情報をどうやって変えるんですか。
吉川 ご存知のように、細菌の繁殖スピードというのは極めて速い。一匹の細菌は、翌日には10の8乗というようなものすごい数になってしまいます。その中に変り者は簡単に出るんです。個体数が多い分だけ、率は低くても間違いなく出て来る。その変り者の中に極めて少数でも、ある薬が効かない菌が出れば、それが生き残ってバーット拡がっていくことになります。
──人間の研究スピードじゃ、とても追い付きませんね。
細菌から別の細菌へ、耐性遺伝子が伝達されていく
吉川 抗生物質が効かなくなるもう一つの要因は、細菌が染色体とは別に持っている小さな遺伝体、これを「プラスミド」と言いますが、このプラスミドの活動によるもので、実はこちらの方がむしろ重要なんです。
問題なのは、プラスミドを持っている細菌から持っていない細菌へ、プラスミドが移行するということです。しかもそれは、例えば大腸菌から赤痢菌へ、といった具合に、まったく種類の違う細菌間にも起こり得るのです。
どういうことかと言いますとある細菌が持っているプラスミドには、いろいろな薬に対する耐性の遺伝子が乗っかっています。その細菌が他の細菌と接合しますと、このプラスミドが接合した細菌に乗り移っていくというわけです。
──その細菌も同じ薬に対し耐性を持つことになるわけですね。
吉川 そうです。そしてどんどん拡がっていくんです。
もっと困ったことは、プラスミドの上には一つではなくて複数の耐性遺伝子が乗っていることが多いんです。ですから、ある細菌のプラスミドが、Aという薬に対する耐性遺伝子、同じくB耐性遺伝子、C耐性遺伝子を持っているとすると、そのプラスミドが他の細菌に乗り移っていくと、Aだけではなくて、BやCの耐性遺伝子も一緒に伝達され、その細菌もいっぺんにA、B、Cの薬が効かなくなるというわけなんです。
これを「多剤耐性菌」と言います。
──そして、これもまたうじゃうじゃ増えていくわけですね。困ったことですね。
吉川 ところが、さらに困ったことがあるんです。この耐性遺伝子というのは、細菌の菌体の中で、プラスミドからプラスミドへとぽんぽんと動き回る性質がある。ですから、ある細菌の中にA、Bの耐性遺伝子を持ったプラスミドと、C、Dの耐性遺伝子を持ったプラスミドがいるとすると、ぽんぽん動き回っているうちに、A、B、C、Dの耐性遺伝子を4つとも持ったプラスミドができてしまうというわけです。
──すごい細菌ができてしまいますね。そのプラスミドが他の細菌に伝達されていけば、強力な耐性能力を持った細菌がどんどん拡散、増大していくことになるんですね。
吉川 しかし、これはまだまだ耐性菌の拡がり方のほんの一面に過ぎないんですよ。
一番実害が大きいのは、抗生物質を使ったために耐性を持たない菌が皆殺しされて、耐性菌集団に置き換えられてしまうということなんです。抗生物質の乱用が問題になるのもこのためなのです。

増大し続ける耐性菌に勝つ手段は・・・
──このままでいくと、世の中の細菌が全部選りすぐられて、薬がまったく効かなくなってしまう日というのが来るんでしょうか。
吉川 そういうことですね。今分かっている病原菌で、耐性を持っていないものはまずないと思います。たいていの菌の場合、たくさんある抗生物質の中には確かに効くものもありますが、もはや効かない抗生物質が大部分であるか、少なくとも幾種類かは効かないというのが普通になってきています。
極端なことを言いますと、効く薬はもう残っていないのではないかという菌もあります。現存する耐性菌の状況から見て、近々全部効かない菌も出て来るでしょうね。
──恐ろしい話しですね。人間が細菌に対抗してつくりだした薬に対して、今度は細菌の側が、まさに逆襲を始めたというわけですね。
では、次は人間はどういう手を打ったらいいんでしょうか。
吉川 まず、新しい抗生物質が次々と出て来るのなら当面はなんとかなるでしょう。しかし、当然これもいずれ駄目になりますが・・・。それ以前に、新しい抗生物質が出て来る可能性もないという人もいます。
もう一つの可能性としては、まだ効く抗生物質がある今の状態を存続することができれば、当面そんなに恐ろしいがる必要はないと思います。しかし、それができるかどうかが問題です。
──それができなければ、どうなるんでしょうか。われわれ人間は抗生物質ができる前、細菌に対しては、身体を丈夫にして病気にかからないようにするというような予防手段くらいしか持っていなかったわけです。その時代に逆戻りということになるんでしょうか。
吉川 本当に効く抗生物質がない状況がきた時には、50年前とまったく同じです。多分、もうちょっと悪いでしょうね。昔より衛生観念が欠落しているし、人口が増えていますからね。
考えられる対処法としては、例えば、50年くらい前にはきちんと守られていた衛生観念、ないし公衆衛生的な方法を、一般人の生活にも、医療の世界にも取り入れるということをしなければならないでしょうね。確かに昔に比べると、抗生物質に頼るあまり、そのあたりが非常に雑になっていて、医者にしても、消毒剤で手を洗うといった習慣が疎かになっていることは事実だと思います。
抗生物質の服用を間違うと重症感染症になることも
──それから、お話しを聞いていてちょっと怖くなったのは、私は医者から抗生物質をもらいますと、途中まで飲んで残りをとっておいて、風邪をひいたかなと思った時に服用したりするんです。でもこれは、効く効かないはともかくとして、危険なことでもあるわけですね。
吉川 まったく論外ですね。まず、投与されただけ飲まないで、素人判断でやめるということが論外です。それから、それをとっておいて、まだその薬が有効かどうか、また、別の病気に効くのかどうかも分からないのに服用するというのも論外です。風邪なんかには本来、抗生物質はまったく効きませんし、それを素人が勝手に判断するなどもってのほかです。人間の身体の中には無害な菌もたくさんいます。これらが抗生物質の乱用により耐性を持つことになり、いざ有害な細菌が入ってきた時プラスミドが伝達され、耐性菌をどんどん増やす手助けをしてしまうだけです。
間違うと、そういう薬を飲んだのが原因で、それまで発病しないで抑えられていた重症細菌感染症を発病させることもあるんです。
これは素人の人もそうですが、医者にしても、ともかく抗生物質信仰というのがものすごい。抗生物質を使えば何でもできると思っている。しかし、現実には、これまでお話ししたような理由で、使い方が非常に難しいものなんです。
──私達は今後認識を改める必要がありますね。
吉川 確かに、医学界でも重大なテーマという認識がなくなってしまったことは事実です。従って、残念なことに、この世界には若い研究者も入ってこない、後継者もいません。
──日本はかつて耐性菌の研究では輝かしい功績を持っており、すばらしい研究者もたくさんいました。人間が細菌にやられてしまわないうちに、ぜひとも吉川先生のお力で、若い優秀な研究者を育成していただきたいと思います。よろしくお願いします。本日は大変勉強になりました。ありがとうございました。
 |
| ベストセラーとなった吉川氏の著書『細菌の逆襲』(中央公論社) |
日本細菌学会理事長就任。本対談の翌年、O-157が流行したが、著書『細菌の逆襲』(ph3)および本対談において、すでにその危険性を予告していたことは注目に値する。
 サイト内検索
サイト内検索