こだわりアカデミー
人間は「動物界の一員」という視点から 文化や環境問題を考えていくべきです。
動物界の競争原理
京都大学理学部教授
日高 敏隆 氏
ひだか としたか

1930年東京生れ。東京大学理学部動物学科卒。現在、京都大学理学部教授(動物学)。日本動物学会会長。専攻は動物行動学。主な著書は『人間についての寓話』(74年、思索社)、『チョウはなぜ飛ぶか』(75年、岩波書店)、『ネコたちをめぐる世界』(89年、小学館)など多数。〔訳書〕K.ローレンツ『ソロモンの指輪』(63年、早川書房)、D.モリス『裸のサル』(69年、河出書房新社)他。
1991年2月号掲載
動物界における競争原理は資本主義的
──「種を残す」とは、人間は人間の、カメはカメの「種」を残すというように考えていたんですが、どうも事実とは違うようですね。
日高 そういうことみたいですね。実際、動物たちは彼ら全体の「種」ではなくて、あくまで「自分自身の遺伝子を持った子孫」をできるだけたくさん残そうと一生懸命になっているんです。すると、結局これはシェア争いの話になります。例えば、ある場所に草原があれば、そこに生える草の量は、土地の質だとか、栄養分とかで決ってしまいます。当然、その草を食って育つことができるウサギの数も1000匹なら1000匹と決ってきます。とすれば、その1000匹の中で自分の子孫がなるべく多くのシェアを占めるようにするためには、自分だけが頑張ってもしょうがない。できれば他のウサギが損をしてくれた方がいいし、あるいは叩いてしまった方がいいというわけで、彼らは他のウサギの足を引っ張ったり、邪魔をしたりするのです。
──何だか、人間と同じですね(笑)。
日高 全くその通りです。彼らは何かというと「何とかして自分の」という行動をとっているんです。
そうすると一つ不思議なことは、そんな足の引っ張り合いを繰り返していたら、「種」全体としては損をしないのか、「種」は滅びないのか・・・。
──共倒れになりはしないのかということですね。
日高 ところが、どういうわけかそうはならないんです。種は、環境を破壊されるとか、そんなことがない限り、ちゃんと生き残るというか、安泰にいくんです。
──バランスがとれているといえばそれまでかもしれないけれども、不思議な話ですね。
日高 そういう意味で、非常に面白いと思うのが、社会主義経済と資本主義経済のアナロジーです。社会主義経済というのは、「種」を残すという方式でしょう。ところが、さっぱりうまいこといかない。残すどころではなくて、もはや危うくすらなってしまった。これに対して、自由主義経済というか、資本主義経済というのは競争でしょう。これがあまりあからさまではないにしろ、やはり競争相手を叩いているわけです。ものすごい競争をしている。しかし、その方が経済としてはいいし、発展する。
──まさに、現実はその通りですね。
日高 理屈はどうか分らないけれど、確実にアナロジーはあるんです。ですから、一昨年ぐらいから非常に面白いなと思って見ているんです。ソ連、東欧など社会主義経済が否定されて、みんな資本主義の方に向かっている。これまでは資本主義の競争原理なんて悪の権化だといわれていたのが、それでなければだめだという話にまで変ってきたというのは実に面白い。
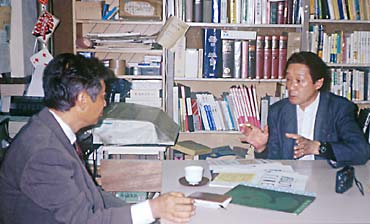
インタビュー後、滋賀県立大学大学長に就任(2001年3月まで)。01年4月からは国立地球環境研究所に就任予定。 また近著に『プログラムとしての老い』(97年、講談社)、『ぼくにとっての学校−教育という幻想』(99年、同)、『帰ってきたファーブル−現代生物学方法論』(00年、講談社学術文庫)がある。 ※日高敏隆先生は、2009年11月14日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)
 サイト内検索
サイト内検索




