こだわりアカデミー
経済統合を目前に控えたヨーロッパは かつてハプスブルク帝国に似ていますね。
結婚がつくった巨大帝国−ハプスブルク朝
比較文化研究者 東洋大学文学部教授
江村 洋 氏
えむら ひろし

1941年(昭和16年)東京生まれ。1970年、東京大学大学院比較文学比較博士課程修了。現在、東洋大学文学部教授。ヨーロッパ文化史、特にハプスブルク家に関する研究を続けている。
主な著書に『ハプスブルク家』(講談社現代新書)、『中世最後の騎士−−皇帝マクシミリアン一世伝』(中央公論社)、訳書に『ハプスブルク家−−ヨーロッパ一王朝の歴史』『女帝マリア・テレジア』(ともに谷沢書房)などがある。
1991年9月号掲載
著書『ハプスブルク家』がベストセラーに
──先生のお書きになった『ハプスブルク家』をとても興味深く、楽しく読ませていただきました。
この本は今たいへんなベストセラーになっていますが、なぜ今、あの時代の、しかもヨーロッパが興味を持たれるのか、ちょっと意外な感じがするんですが・・・。
江村 いろいろな要素があると思いますが、一つには、やはりここ数年のヨーロッパの動きということがあるんでしょうね。今までは、ソ連があって、西欧圏があって、そして東欧圏がありました。ちょっと前までは、ハンガリーやチェコなど国境を越える時は非常に厳しい検査がありまして、旅行者は入国するのがなかなか大変でした。それが、近年の自由化で、今では、例えば、ウィーンとブダペストの間なんか簡単に日帰りできるほどです。
このように、東西関係が緩んできて、ヨーロッパが一つにまとまろうとしつつある状況が、かつてのハプスブルク帝国、すなわちオーストリア帝国のもとでヨーロッパが一つになっていた時代とよく似ているんです。
──なるほど。経済統合に向けて動きが活発になっている現在のヨーロッパに、ハプスブルク王朝のもとでのかつてのヨーロッパがオーバーラップするような感じですね。それで大変関心が高くなっているんですね。
江村 そうなんです。だから『ハプスブルク家』自体は自分なりに勝手に書いたものなんですが、本当に意外な反響があります。ずいぶんいろいろな方が読んでくださって、書評なども書いていただいています。まさに来年がヨーロッパの市場統合ですからね。
ヨーロッパには、ナポレオンやヒトラーに支配された時代もありましたけれども、そもそもヨーロッパは一つ、小さい国家の集まりではあるけれども一つの概念なんだ、という考え方が昔からあります。それが特にハプスブルクの時代には、ヨーロッパ連合といいますか、ヨーロッパは一つにならなくてはいけない、という考え方が強かったんですね。
──ハプスブルク王朝が崩壊した一つの要因は、民族運動だったわけですね。ところが、今度は民族や言語がバラバラな現在のヨーロッパにおいて、全体をまとめていこうという気運が出てきているということは、これまたおもしろいなぁと思っているんです。
江村 そうですね。その意味では昔のハプスブルク帝国が、一つのモデルのようなものですよね。確かに、第一次世界大戦まではオーストリアを中心として、チェコスロバキア、ハンガリー、ポーランド、それからイタリアやもちろんドイツの一部も含めて、10いくつもの民族が一つのハプスブルク帝国というものの中に含まれていた。民族や言葉はバラバラだけれども、それにもかかわらず、全体としてハプスブルク帝国の支配下にあって、例えば鉄道などはみんなウィーンと直結している。そして、鉄道員の着ている服とか信号や旗の振りかたなどはすべて、ハプスブルク帝国の末端まで同じだったわけです。
また逆に、ハプスブルク帝国という中にあって、各民族は、小さくても、ある程度独立が保たれていたんです。
──なるほど。今のヨーロッパの状況にぴったり合いますね。
江村 そうですね。
結婚によって次々と領地を拡大
──もう一つおもしろいなぁと思ったのは、ハプスブルクという家系です。王家とはいえ、一つの家なんですよね。それが、周囲にいろいろな王家、豪族等列強がいる中で、神聖ローマ帝国の皇帝として、代々その地位を維持し続けたというのは不思議というか、一体どういうことなのかと思いましてね。
江村 もともとハプスブルク家なんてものは、スイスの国境に近い、今でいうとバーゼルあたりのドイツ領の小さな豪族のようなものに過ぎなかったんです。それが、どうして支配者になれたか。すなわち、婚姻です。ハプスブルクは、結婚というものがうまく当たったんです。
──うまく当たった・・・?(笑)
江村 王家の結婚というものは、生きるか死ぬかの分かれ目のようなもので、ヘマをすると、自分の国を取られてしまうわけです。常に王子がいれば問題なく継承でき、国家が続いていくけれども、たいていの家はどこかでこれが崩れてしまうわけですね。つまり、男の子が生まれなくなってしまう。
しかし、ハプスブルクだけはうまい具合に男の子がずっと続いたんです。その上、結婚運が非常に良かった。例えば、スペインがハプスブルクのものになった時もそうでした。スペインを相続するはずの王子たちが、皮肉にもバタバタ死んでしまい、残ったのは、フアナ王女一人。その夫であるハプスブルクのフィリップがスペインの王位を継いだんです。それでうまい具合にスペインを乗っ取ってしまった。今のハンガリーとかチェコスロバキアにしても同様です。結局、マリア・テレジアの父親であるカール6世まで非常にうまく続いたんです。そして領地を拡げていったわけです。
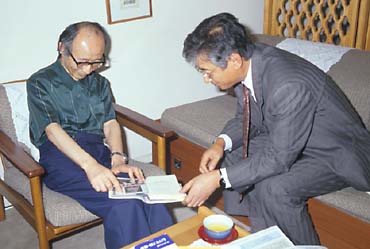
19年半で16人出産した女帝マリア・テレジア
──マリア・テレジアは女帝ですが・・・?
江村 カール6世が相続順位法を制定して、この長女による継承を諸国に認めさせたんです。ただ、これはカール6世の死後、「オーストリア継承戦争」を引き起こしてしまうんですが・・・。
──でも、この女帝の政治力は並はずれていたんですよね。
江村 そうなんです。その上、この女帝も、家系を守るために、自ら、なんと16人も子供を産んだのです。
──それはすごい。
江村 それも、初めて子供を産んだ時から最後の16人目を産んだ時まで、正味19年半くらいなんですね。
──常に妊娠しては出産を繰り返していたことになりますね。
江村 そうですね。容姿もすばらしいが、身体もとても丈夫な人だったようです。本当か嘘か、4人目の子供のヨーゼフ(2世)を産んだ時、「2−3か月のちに次の子供が産めればいいのに」と言ったと言われています。
──先般、この対談で、京都大学の日高先生にお話を伺った時、すべての動物は一生懸命に直系の子孫を残そうとしていて、それをフィットネスと言うんだ、と教わったんです。われわれは最近「家」についてはほとんど考えなくなってきましたけど、そういうふうに考えますと、歴史そのものも、直系を残していくというか、家を残していくというエネルギーがいろいろなものを生んでいると思うんです。政治の場合、それが必ずしもいい方向に行くとは限りませんけど、そういうエネルギーってすごいなぁ、と。
江村 それは本当にすごいです。またそれだけ、君主にとっては切実な問題なんですよ。先程お話ししたマリア・テレジアのお父さんのカール6世には女の子しかできませんでした。しかも彼の后は身体が弱くて、男の子はおろか、もうとても子供を産める状態ではなかったわけです。けれども、当時のキリスト教世界では死なないかぎり決して離婚できない。ですから彼は、後継者はどうなるか、国家はどうなるか、と悩み続けたわけです。
イギリスのヘンリー8世も同様でした。后のカトリーナが弱くて、とても男の子はできそうにない。そこでなんとかして離婚して、自分がかわいがっている宮廷の女官と結婚したいと、ローマ教皇に金の力で離婚を認めてもらおうとしたんです。
ローマ教皇がしっかりしていた時代であれば、そんなことは認められないわけですが、ルネッサンスの時代にはローマ教会、キリスト教というのは非常に堕落しておりましたので、教皇なども金の力に弱かったんですね。
──商売みたいになっちゃっていたんですね。
江村 はい。金で特例として認めてやったりしたわけです。
このあたり、ヨーロッパの歴史のおもしろいところですね。
──王家の後継者問題が、宗教や、政治にまで影響していくというのは、何かすごく人間的なものを感じますね。
宗教にとらわれないものの考え方に注目が...
──ところで、宗教と言えば、今、ヨーロッパが一つにとか、世界が一つに、と言われている中で、民族や言語の壁は越えられても、最終的に障害になるのは、私は宗教ではないかと思うんですが・・・。
江村 なるほど。そうかもしれませんね。
──ですから、これからの時代は宗教を持たないというか、宗教にとらわれない人たちが大事な役割を果たすのかな、とも思うんです。
江村 確かに、今のヨーロッパの精神というものは、これまでの世界の指導的な立場という意識から変わりつつありますね。無宗教とか、神なんてものにとらわれないものの考え方が見直されるというか、注目される、そんな流れが出てきています。日本なども、東洋のエキゾチックなイメージと同時に、あまり宗教観を持たない国、そして世界の経済大国でもあるわけで、ヨーロッパ人の中にも日本のいろいろなものを見聞きし研究する風潮が出てきています。
──日本を研究することが、経済統合を間近に控えたヨーロッパにとって、参考になる、あるいは何かを示唆するものになるんでしょうか。いずれにせよ、ヨーロッパ統合でヨーロッパ自身、そして世界がどう変わるか、興味深いですね。
楽しいお話をありがとうございました。
著書 『ハプスブルク家の女たち』(1993年6月、講談社現代新書) 『マリア・テレジアとその時代』(1992年、東京書籍) 『カール五世 中世ヨーロッパ最後の栄光』(同) 『フランツ・ヨーゼフ ハプスブルク最後の皇帝』(1994年、東京書籍) 訳書 『ハプスブルク夜話 古き良きウィーン』(1992年、河出書房新社) 『ハプスブルク家史話』(1998年東洋書林) 『ハプスブルク家の愛の物語』(1999年、東洋書林) ※江村 洋先生は、2005年11月3日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)
 サイト内検索
サイト内検索




