こだわりアカデミー
幕末から明治初期にかけた動乱の時代、 「出雲」は重要な役割を果たしたのです。
近代日本に影響を与えた「出雲」
明治学院大学国際学部教授
原 武史 氏
はら たけし

1962年東京都生れ。早稲田大学政治経済学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程中退。国立国会図書館職員、日本経済新聞社東京社会部記者、東京大学社会科学研究所助手などを経て、1997年山梨学院大学法学部助教授、2000年明治学院大学国際学部助教授、04年より現職。08年4月より同附属研究所所長も務める。専門は日本政治思想史。著書『「民都」大阪対「帝都」東京――思想としての関西私鉄』で、サントリー学芸賞社会・風俗部門、『大正天皇』で第55回毎日出版文化賞、『滝山コミューン一九七四』で第30回講談社ノンフィクション賞、『昭和天皇』で第12回司馬遼太郎賞などを受賞している。近著に『団地の時代』『沿線風景』『「鉄学」概論』など。
2011年2月号掲載
「近代の動き」を政治思想史からみる
──「出雲」は近年、相次いで遺跡が発見されるなど古代ロマンの地として、また、近頃はパワースポットとしても何かと話題です。
考古学や国文学、民俗学といった分野も大変興味深いのですが、先生がご著書『〈出雲〉という思想』の中で、「政治思想史」という面からアプローチしていらっしゃるのを知り、とても新鮮に感じました。
 |
| オオクニヌシを祀る出雲大社(島根県出雲市)。平安中期に源為憲が著した貴族子弟のための教科書『口遊』では、東大寺大仏殿、平城宮の大極殿と併せ、当時最も大きな建造物として紹介されている〈画像提供:出雲大社〉 |
出雲については後程いろいろと伺いたいのですが、まずは、先生のご専門である、政治思想史について教えてください。
原 例えば、われわれが普段何気なく使っている、「自由」や「正義」、「民主主義」という言葉や考え方について、歴史的に検証していく作業だと私は思っています。いま話題になっているマイケル・サンデルの『これから「正義」の話をしよう』もそうですね。
分りやすくいうと、国家や政府、権力の存在を肯定的にせよ否定的にせよ踏まえたうえで、どういう統治のあり方が一番望ましいと考えられたのかを検証するものです。
──そのような検証を通して、これからの体制のあるべき姿を考えるということでしょうか?
 |
原 突き詰めていくとそうなるのかもしれませんが、そのためには過去の叡智から学ぶ必要があります。古今東西を問わず、これまでにどういう思想があったのか、その経緯を細かく見る必要があると私は考えています。
例えば、日本の場合、江戸時代の後期に日本固有の文化や思想をしっかり見直そうという「国学」の動きが起こり、本居宣長によって大成されました。それが、平田篤胤に受け継がれ、復古神道が台頭するようになります。一般に復古神道は尊王攘夷運動や倒幕運動のイデオロギーとなり、明治維新で新政府が樹立され、王政復古の大号令が発せられると、皇祖アマテラスが祀り上げられたとされています。
──平田篤胤の復古神道は、日本固有の精神に立ち返ろうという思想だったと記憶していますが・・・。
原 そうです。
ただ、私は、こうした一連の動きについて、「そうした見方だけでは少し単純すぎやしないか」と思っているんです。
──といいますと?
原 幕末から明治維新にかけて、実は〈出雲〉が思想史的に重要な役割を果たしたのです。
日本書紀の「国譲り」では、条件交渉がなされていた!?
──本題に入る前に、すこし整理させていただきたいのですが、「出雲」といえば、出雲大社の主宰神である「オオクニヌシ」を連想します。
そして、日本の国の興りについて伝える「古事記」や「日本書紀」の中では、オオクニヌシが、アマテラスの孫・ニニギに国土を譲り隠退した「国譲り」が伝えられていますね。
「古事記」や「日本書紀」では、伊勢神宮の祭神・アマテラスが最高神的な存在のように感じるのですが、「譲る」ということは、もともとはオオクニヌシが統治していた、ということですか?
原 「国譲り」については、日本書紀をきちんと読んでみると、大変興味深い発見があります。
正史と認められている日本書紀は、本文のほか、それに添えられる「一書」という形で、多くの異伝、異説が書き溜められているのですが、国譲りに関する限り、本文と異説部分である「一書第二」では、書かれている内容がずいぶん異なるんです。
──具体的には?
原 日本書紀の本文では、アマテラスの勅によって、オオクニヌシが国土を皇孫にすんなり譲っています。
しかし、「一書第二」では、オオクニヌシがアマテラスの使者から「あなたが行なわれる『顕露の事』はアマテラスの孫のニニギが治めるようにしましょう。その代わり、あなたは『神事』を治めてください」といわれており、オオクニヌシは「私が治めるこの世のことは、ニニギが治められるべきです。私は退いて『幽事』を担当しましょう」と返答した様子が描かれています。
 |
| オオクニヌシの子とされるタケミナカタと高天原から遣わされたタケミカヅチが力競べをしたという「国譲り」神話の舞台・稲佐の浜〈画像提供:(社)島根県観光連盟〉 |
──つまり、条件交渉というか、役割分担をしてお互いが譲りあったというわけですね。
私はオオクニヌシはニニギに国を譲って尻ごみするように隠退し、支配権を一切失ったように理解していました。
ちなみに、「顕露の事」、「幽事」とは何を指しているのでしょうか?
原 平田篤胤は、「顕露の事」とはこの世(現世)での治政、「幽事」とは冥府(あの世)を治めることと解釈しています。
さらに、「顕」の治政者も、いずれは死んで「幽」の世界に行き、幽を治める者の支配下に入るのだから、「顕」に対して「幽」の方が優位であり、アマテラスよりオオクニヌシの方がえらいのだと主張しました。
──伊勢神宮の下に全国の神社を階層的に組織編制した国家神道とは違った解釈ですね。
原 そうなんです。この、オオクニヌシを中心とする篤胤独自の神学が投げ掛けた波紋は大きく、それがやがて明治初期に宗教論争を引き起こすことになったのです。
近代日本にも宗教論争があった!
──この近代に宗教論争があったんですか!? 驚きです。
原 1867年の大政奉還に続き、新政府は「祭政一致」を標榜し、古代の神祇官を再興する方針を出しました。つまり、神道の立場が急速に高まったわけです。
──そうすると、どの神を主宰神として祀るかで、争いが起きる・・・。
原 ええ、オオクニヌシを神道事務局の祭神に加えるべきか否かをめぐる祭神論争が起きました。
復古神道に基づいてオオクニヌシを合祀すべきだとする「出雲派」に対して、「伊勢派」は出雲派の主張を「国体」に反するものだとするなど、論争は混迷を極めました。
出雲派の中心となったのは、出雲大社の大宮司で、八十代国造を名乗る千家尊福でした。一方、伊勢派の中心となったのは、田中頼庸や浦田長民ら、伊勢神宮の神官達でした。
──しかし、先生が先程おっしゃった日本書紀の「一書第二」の部分を読むと、出雲派が有利ですね。
原 そうです。実際、純粋な神学論争として見れば、出雲派に有利な状況で展開されていきました。
そこで危機感を感じた伊勢派は、出雲派よりも権力に近かった立場を利用して、天皇の勅裁を仰ぐよう働き掛けたのです。
──そして、伊勢派が勝利し、第二次世界大戦終戦まで、国家神道として国家主義思想を支えたのですね・・・。
原 その通りです。神道は宗教でないとした国家神道が確立される背景には、祭神論争をきっかけとする〈出雲〉の抹殺があったと見ています。
──出雲の神々は今も人々の心のなかで脈々と生きていますが、近代において、出雲はいろいろな形で関わっていたわけですね。
 |
| 出雲大社は毎年、この海辺(稲佐の浜)で全国より参集する神々を迎える「神迎祭」を執り行なっている〈画像提供:出雲大社〉 |
今回は先生のお話を伺って、近代をまた別の角度から眺められるようになったような気がします。いろいろな視点から、物事を見ていく大事さを、改めて実感しました。
本日は、どうもありがとうございました。
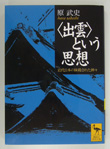 |
| 『<出雲>という思想』(講談社) |
 サイト内検索
サイト内検索




