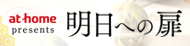こだわりアカデミー
生きながらにして「生と死を統合」する、 それがホリスティック医学が目指すものです。
生と死を見つめるホリスティック医学
帯津三敬病院名誉院長
帯津 良一 氏
おびつ りょういち

1936年埼玉県生れ。61年東京大学医学部卒業。東京大学医学部第三外科、都立駒込病院勤務を経て、82年埼玉県川越市に帯津三敬病院を開設し院長となる。人間をまるごと捉える「ホリスティック医学」の確立を目指し、医療の東西融合という新機軸を基に、癌患者などの治療に当る。また、気功、漢方薬、鍼灸、食事療法、心理療法、健康補助食品などの代替医学も積極的に治療に取り入れている。講演や大学での講義を行なうほか、日本ホリスティック医学協会会長、世界医学気功学会副主席、上海中医薬大学客員教授、調和道協会会長等を務める。著書に『ガンを治す大辞典』(二見書房)、『健康問答』(五木寛之氏との共著、平凡社)、『健康になる格言』(草思社)、『ホリスティック医学入門』(角川書店)など多数。
2010年2月号掲載
再発予防こそ重要なもの。心、体、生命一体の治療へ
──先生は、西洋医学に東洋医学や代替療法を取り入れた、「ホリスティック医学」の確立を目指して、癌患者さんの治療に当っていると伺っております。
帯津 ホリスティック医学は、心、体、生命の3つを一体として治療していく、いわば人間をまるごと診る医学です。
その一環として、私は病院内に道場を設けて、毎日、気功や太極拳などの教室を開いています。患者さん達の癌の増殖を抑えるために30年程前から始めたのですが、今ではたくさんの患者さんが道場に足を運び熱心に取り組んでくれています。
──気功や太極拳は、今でこそ健康法として市民権を得ていますが、先生が始められた当初は、癌の治療法として理解してもらうのは、大変だったのではないでしょうか。
帯津 そうですね。始めた当時は「気功で癌を治そう」といっても、ほとんどの方が「そんなことで癌が治るはずがない」と、興味を示してくれませんでしたね(笑)。
それでも続けていくうちに、参加者の人数も増えていき、中には驚くような回復を見せる患者さんが出てきたのです。
──先生がそうした取組みを始められたきっかけは?
帯津 私が医者になった1962年頃は、西洋医学の発展が目覚ましく、やがて癌は撲滅できると希望を持っていました。しかし、時が経って、いくら医学が進歩して、どんなに完璧と思えるような手術をしても、数か月後には再発してしまう患者さんが後を絶ちませんでした。西洋医学に限界を感じた私は、今までとは違った視点が必要だと思い、80年頃から中国医学について調べるようになったのです。当時はまだ閉ざされた国でしたが、中国の医療施設を数か所見て回ると、癌治療に気功を応用して再発を予防していることなどを知りました。私は再発予防こそ、癌治療にとって重要なものだと感じ、82年に気功を治療に取り入れるために、道場を併設した病院を開設したのです。
──気功には、体内の『気』の働きを活性化させたり、バランスを整えて、自然治癒力を高める効果があるそうですね。
 | |
| 帯津三敬病院では、希望する患者さんに、気功、呼吸法、太極拳などの健康法を実践できる場を設けている。人体の自然治癒力を発揮させ、病の早期感知の手助 けとなるよう行なっており、退院後も通院治療を兼ねて実践する人が多いという。写真は道場や屋外で帯津先生が呼吸法の教室を開いている様子〈写真提供:帯 津良一氏〉 |  |
帯津 はい。驚くべきことに、気功をしている人の方がしていない人に比べ、術後の生存率が高かったのです。癌は治療した後にも転移する可能性のある病ですが、その頃の日本では、術後の再発予防など、ほとんど行なわれていない時代で、私は目の覚めるような思いがしました。
死と向き合うことで死への恐怖が消える
──先程、西洋医学に限界を感じられたとのお話でしたが・・・。
帯津 癌治療には、これをすれば必ず治るというものはありません。反対にこれをやらなければならないというものもありません。
西洋医学では、手術、抗癌剤、放射線などの治療が行なわれますが、視野を広げれば、東洋医学や代替療法を組み合せるなど治療法はいくらでもあるのです。
──そういうことは一般の患者さんには分りませんね。医者にいわれるがままに治療して、苦しい思いをする方も多いと思います。患者さんとしては、自分が納得いく治療法を選んでいきたいものですが…。
帯津 それから、「あなたの余命は三か月です」と告知する医者がいますが、私は病名告知は必要だと思いますが、余命告知はしてはいけないと考えています。なぜなら、その人の余命など誰にも分らないからです。三か月といわれた人が何年も元気で生きたという例はいくらでもありますし、はっきりとしないことを決まっているかのように断言して患者さんの希望を奪ってしまう権利は、どんな優秀な医者にもないからです。
 |
| 〈写真提供:帯 津良一氏〉 |
──もし癌だと宣告されたら、私達はどのような心構えをしたら良いのでしょう。
帯津 私は青木新門さんの著書「納棺夫日記」(話題となった映画「おくりびと」の元となった作品)の中の、「末期者には激励は酷で善悪は悲しい。説法も言葉も要らないのだ。きれいな青空のような瞳をした、すきとおった風のような人がそばに居るだけでいい」というくだりが印象に残っています。
「すきとおった風のような人」とは、死の恐怖に怯えている人よりも一歩前の死に近いところにいる人、つまり死のことをよく考えている人だと、新門さんはいいます。それは、日頃から自分の死について、考えている人だと私はとったんです。
死のことはできれば考えたくないものですが、死から逃げるのではなく、真正面から向き合うことで、死への恐怖が消えると思うのです。
──確かに、普通の人は、癌を告知された途端に突然、死が現実化して、ものすごい不安、恐怖となりますからね。
帯津 ええ。ところが、死後の世界はすばらしいものだということを、心の奥深いところで納得できるようになった患者さんの中には、体調がみるみる良くなっていく方がたくさんおられます。
──死と対峙したことによって、自然治癒力のスイッチが入ったのかもしれませんね。
帯津 ですから私は、医者も看護師も、死に直面している患者さんと接する機会のある人は、常に自分の心の中で、きちんと死を受け入れて、「すきとおった風のような人」にならなきゃいけない。医者はエリート意識を振りかざすのではなく、患者さんと同じ目線で付き合うようになるべきだと思っています。
医療の中で、もっと死について語るべき
──ところで、先生が目指すホリスティック医学の目標とは・・・。
帯津 ホリスティック医学の究極は、「生と死の統合」です。生きながら死を考えることで、自分はどんな人生を送りたいかが見えてくる。それは闘病にも大きな影響を及ぼします。
──私達は、生と死を切り離して考えがちですが、先生のおっしゃる生と死の統合のためには、何が必要でしょうか。
帯津 死について、医療の中でもっと語るべきだと思います。いずれは死ぬんだということを考えることで、死は別に怖くなくなる。私は、死ぬということを患者さんに積極的に語るようにしていますが、道場でそういう話をするとみんなにこにこしながら聞いてくれます。
──いずれは来る「死」を考えることで、そこに至るまでの「生」についても明確になる。自分の生を充実させて、完成させたという思いで、死んでいくことができれば、死を忌み嫌う必要はまったくないわけですよね。
帯津 そうです。患者さんにもそういう人が増えているんですよ。
ある患者さんは、回診にいったら、ベッドの上に正座して、「今日は最後のご挨拶をしようとお待ちしておりました。私はあと2、3日だと思います。最後にいい医療を受けさせていただきました。先生のお陰です」といって握手を求めてきました。その患者さんは、本当に3日後に亡くなったのです。
また、3回目の入院をしてきたある方は、もうかなり弱っていたのですが、私が治療のための「戦略会議」に行くと、にっこりと笑って、「今日の戦略会議は、治すための戦略会議ではなく、虚空に行くための戦略会議にしてください」というのです。そこで、虚空というものはこういうものだという話をしましたら、にこにこして聞いていました。翌日行くと、もう意識がなく、何もいえない状態で、その次の日に亡くなりました。思い出してみると、あの方達は、死の手前で生と死が統合されたような気がするんです。
──きれいな死に方というか、自然ですばらしい逝き方ですね。
 |
帯津 僕は映画少年だったので、ずいぶんたくさんの映画を観てきましたが、いい映画のラストシーンは、必ずすばらしい。だから人生のラストシーンもきちんとしなきゃだめだと、日頃からみんなにいっているんです。充実した人生を過ごして最後にしくじるのはやはり残念だと思いますから。
──私も自分の理想の死に方についてイメージして、それに近いラストシーンを迎えられるようにしたいと思います。
本日はありがとうございました。
 |
| 『生きる勇気 死ぬ勇気』(平凡社) |
 サイト内検索
サイト内検索