こだわりアカデミー
どんなに科学や社会が進歩しても「限界」はある。 最後は「不条理」としかいいようがない!?
「限界」を知ることの面白さ
國學院大學文学部外国語文化学科教授
高橋 昌一郎 氏
たかはし しょういちろう

1959年大分県生れ。83年ウェスタンミシガン大学数学科・哲学科卒業。85年ミシガン大学大学院哲学研究科修士課程修了。86年東京大学研究生、88年テンプル大学専任講師、92年城西国際大学助教授。96年國學院大学助教授、2001年同大学教授、現在に至る。論理学、科学哲学、ディベート論、コミュニケーション論、限界論、クルト・ゲーデルなどについての著書・論文多数。主な著書は『東大生の論理−「理性」をめぐる教室』(ちくま新書)、『ゲーデルの哲学』『理性の限界』『知性の限界』(講談社現代新書)、『哲学ディベート』(NHKブックス)、『科学哲学のすすめ』(丸善)、『環境と人間』(共著、岩波書店)、『パラドックス!』(共著、日本評論社)など。
2011年5月号掲載
論理的ディベートで「限界」の核心に迫る!
──先生のご著書『理性の限界』『知性の限界』を、大変興味深く拝読させていただきました。
先生のご専門は論理学と伺っていましたので、実際に読むまでは「難しいんじゃないかな・・・」と思っていたのですが。いやはや、とんでもありません。大変面白く、そして時に難しく(笑)、とても楽しく読み進むことができた1冊でした。
また、さまざまな登場人物が「パネルディスカッション形式」で議論しながら、人類が到達した「限界」の核心に迫っていく、という構成も、大変ユニークで斬新だったと思います。
 |
高橋 ありがとうございます。
私が最大の目標にしたのは、読者の方々に「知的刺激」を味わっていただくこと。それと併せて、あくまで「楽しみながら考えてもらう」ことを優先したつもりです。従って、シンポジウムの参加者も、各分野の専門家だけではなく、会社員や運動選手といった普通の人も登場させました。
もちろん、とかく専門書に頻出しがちな専門用語は極力使わず、例えば、ちょっと難しい言葉が出てきたときには、会社員に「分りません!」と突っ込みを入れさせ、それに対して専門家が「では、分りやすくご説明しましょう」といって解説するような形式になっています。
──確かに、難解で聞き慣れない用語が少なく、非常に分りやすかったです。それに、時々「カント主義者」や「ロマン主義者」などが極論を示して話が飛躍するせいで、ハッとさせられることもあり、興味が薄れることがありませんでした。
高橋 彼らの発言の中には、かなり飛躍したところや厳密性に欠ける部分も含まれていましたが、難しいテーマに興味を持っていただくために、あえて登場させたのです。
「限界」を知った上で閃く発想の面白さ
──ところで、そもそも先生はなぜ「限界」というテーマに興味を持たれたのでしょうか。
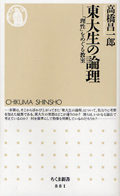 |
| 『東大生の論理−「理性」をめぐる教室』(ちくま新書) |
 サイト内検索
サイト内検索




