こだわりアカデミー
帰化動物は、好き勝手に日本にやって来て 問題を起こしている訳ではないんです。
帰化動物はなぜ増える?
神奈川県立生命の星・地球博物館前学芸部長
中村 一恵 氏
なかむら かずえ

1940年、栃木県生れ。64年、東京水産大学増殖学科卒業。65年より神奈川県立博物館学芸員を経て、95年より神奈川県立生命の星・地球博物館勤務。同年、同館企画普及課長、98年より同館学芸部長。2000年、定年退職。現在、同館非常勤学芸員。著書に『スズメもモンシロチョウも外国からやって来た−帰化動物と日本の自然』(90年、PHP研究所)、『帰化動物のはなし』(94年、技報堂出版)他。
2001年11月号掲載
ペットになり得ない生物もいる。理解と責任こそが飼い主の使命!
──最近は、捨てられたペットが野生化してしまうという例も多いようですね?
中村 野生の生物をペットにするようになってから、この問題は増えてきました。
──物質的にゆとりがあるから、「お金を出して珍しい種を」なんて考えるんでしょうか?
中村 人間は動物を支配するようになって、まず動物を見たいという欲求が湧きました。それにより、世界の至る所に動物園ができたわけです。そしてその次には、触ってみたい、飼育してみたいとなるのが人間の心理なんです。
 |
| 動物園から脱走し帰化動物となったタイワンリス |
──それが高じて、ペットとしてふさわしくない生物でも飼ってみたいと思う人が出てきたわけですね。
中村 ええ、しかしどんなに努力やケアをしても、家畜になり得ない生物がいるということを理解しなければなりません。どんな動物でも、犬や猫のようにペットになるとは限りません。
アライグマがその良い例です。確かに小さい時は可愛いのですが、成長するに従ってその獰猛さは手が付けられなくなります。このように、生物の習性をきちんと理解しないままペットにしてしまうから問題が起こる。逃げられてしまったり、手に負えないと捨ててしまったりする人も出てくるわけです。
──もともと野生の生物ですから、そこが暮しやすければ定着し野生化するのは当然というわけですね。
中村 その通り。だからきちんと法制化して、生態系を撹乱するような生物の移入を防がなければならないんです。
しかし、この問題は何も日本に限ったことではなく、人間のグローバル化に伴って、世界中で生物のグローバル化が起こり、環境破壊や生物の絶滅危機に拍車を掛けたりと、非常に問題になっています。
しかしその中でも、日本は特に危険なんです。
──それはまた、どうして?
中村 日本人は情にもろいせいか、問題解決策として駆除しようということになっても、欧米に比べ、なかなかパッと切り替えることができません。「可哀想だ」「こっそり逃がそう」という発想をする人が少なからずいるんですよ。そして、そういう行為が、帰化動物をさらに増やしてしまう…。
──かつては海溝や砂漠、山脈などの自然環境が、移入を防ぐバリアとなっていたわけですが、交通手段の発達した現在においては、法をバリアにしなければ帰化動物の増加による被害は食い止められない状況になってしまったということですね。
中村 残念ながらそういうことです。ですから、人為的な生物の移入がいかに危険なことなのかを教育していく必要があります。
 |
| お祭りの定番「ミドリガメ」は成長するとアカミミガメに |
そもそも生物を商品化するということ自体、戒めるべきことだと思いませんか?
──おっしゃる通りです。また、輸出入等に対するチェックもさらに厳しくする必要がありますね。
先生は、日本哺乳類学会移入動物対策作業部会委員というお立場で、さまざまな問題に取り組まれ、ご苦労が多いことと思いますが、少しでも良い方向に問題が解決されることを願っております。
本日はありがとうございました。
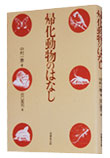 |
| 『帰化動物のはなし』(技報堂出版) |
 サイト内検索
サイト内検索




