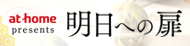こだわりアカデミー
渋沢敬三先生の陰徳の精神は 現代の日本人が忘れてしまったものの一つかもしれません。
忘れられた偉人・渋沢敬三と「陰徳の精神」
文化人類学者
飯島 茂 氏
いいじま しげる

いいじま しげる 1932年、横浜生れ。55年、東京教育大学卒業、61年、京都大学大学院修了。法学博士。専攻は社会人類学。主な著書に、『ネパールの農業と土地制度』(東京大学出版会)、『カレン族の社会・文化変容』(創文社)、『祖霊の世界−−アジアのひとつの見方』(NHKブックス)など、多数。
2005年6月号掲載
経済人、パトロン、学者、3つの顔をもつ「渋沢敬三」
──先日、先生が渋沢敬三さんについて執筆された新聞記事を拝見し、大変感銘を受けました。敬三さんは日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一さんのお孫さんであったわけですが、飯島先生のご専門でもある人類学や、民俗学、地理学といった学問に多大な貢献をされた方だということを、実は初めて知りました。まさに偉人ですね。
飯島 そうなんです。なぜ、このような人が世間であまり知られていないのかと、時々不思議に思うのです。
もし、この方がいらっしゃらなかったら、日本の文化人類学や民俗学といった学問は、今よりかなり遅れていたでしょうね。
──経済人であり、政治行政も行ない、学界のパトロンであり、さらにはご自身も大変な学者だったそうですね。
飯島 そうなんです。
 |
| 写真右が1929(昭和4)年当時の渋沢敬三(1896−1963)氏。本牧沖にて釣り上げた鯛と <写真提供:渋沢史料館> |
敬三先生は「渋沢栄一の孫」としてお育ちになりました。幼少の頃から生物や動物といったものへの関心が非常に深く、ご本人はその道を進みたかったようですが、周囲の方、とくに祖父・栄一氏の懇願があって、ご本人があまり望まれていなかった実業の学問を学ばれた方でした。
第一銀行頭取、第二次世界大戦末期の日銀総裁、敗戦後疲弊した日本経済下で大蔵大臣などを引き受けられ、財閥解体を行なうなど、日本経済が大変な時に多大な尽力をされた経済人です。
しかしその一方で、ご自身の学問やその支援を諦めずに続けられていたんです。
──というと?
飯島 例えば、ご自身で収集された膨大な数の民俗資料をもとに、ご自宅に「アチックミュージアム」(屋根裏博物館)を開設されました。これは、多くの有能な研究者を輩出し、また、100以上もの出版物を残しました。ちなみにこの「アチックミュージアム」は現在の国立民族学博物館の原型でもあるのです。
また、ご自身が発見された旧家文書を解読し、『豆州内浦漁民資料』として大著を仕上げられるなど、一流の研究者でもありました。
 |
| (上)石垣島のタターチャ漁の様子を敬三氏が撮影したもの。同氏はこと漁法や漁民の生活について関心が高かった。 |
それだけに留まらず、柳田国男・岡正雄らとともに創刊した「民族」という学術誌のスポンサーを始め、人類学・先史学・民族学・民俗学・社会学・宗教学などの若手研究者の留学費用や研究費用を自費で負担されたり、苦学生を自宅に置いて面倒をみられたそうです。
──例えばどんな研究者が?
飯島 研究者の学問分野や考え方などは一切問われなかったそうです。直接・間接的に援助を受けた学者は、民俗学の宮本常一や民族学の岡正雄に加え、「花祭」の研究で有名な民俗学の早川孝太郎、河童や日本文化を研究した民俗学の石田英一郎、アジアや南米でフィールドワークを積んだ文化人類学者の泉靖一、日本の霊長類学の創始者である今西錦司、チベット・ネパールを研究した民族学の川喜田二郎、国立民族学博物館初代館長の梅棹忠夫、社会人類学者の中根千枝、アイヌ研究の金田一京助、熊野の山々を調査した南方熊楠等々数えきれません。
これは晩年に敬三先生ご自身もおっしゃっておられますが、今の金額にして100億円くらいは支援されたそうです。
経済的なこともそうですが、敗戦後しばらくは今のように誰でも気軽に海外へ留学や研究に出向ける時代ではありません。敬三先生のご手配やお口添えがなければなかなか難しく、そういった面でも実にご尽力なさったようです。
「謙虚」と「他利の精神」と
──先生もその中のお一人で?
飯島 私も若い頃、晩年の敬三先生にお世話になったことがあります。
西北ネパール学術探検隊(隊長:川喜田二郎氏)の一員として、ご支援いただいた渋沢先生の自宅にお礼に伺った際、「ヒマラヤでは何を食べてたんだね? うまいものでも食べにいこう」と歓迎してくださいました。しかし考えてみると当時の敬三先生は、ご自身で立案された財産税により資産のほとんどを失われ、経済的にも非常に苦しまれていた状況だったのです。ご自身は渋沢財閥の御曹子とも思えないような質素な家にお住まいになりながら、自費で援助を続けてくださった。その上、まだ駆け出しの若い研究者をねぎらってもくださったわけです。心遣いが行き届く方で、本当に温かいおもてなしを受けました。
また、私たちがチベット人の風習である「鳥葬」の撮影に初めて成功したことを大変に喜んでくださいました。そして、敬三先生がアメリカへのご出張の際に、なんとそのフィルムをライフ誌に持ち込み、掲載を交渉してくださったのです。しかし実際には、その写真は掲載されませんでした。というのも、その当時の日本製のフィルムはアメリカ製のものと比較すると性能が非常に悪く、出版する印刷物としては使い物にならないといわれたそうです。
 |
| (写真左)鳥葬の様子。遺体は鳥の食べやすいように解体される。一夜明けると背骨と腰骨とお守りのみ残る<写真提供:飯島茂氏> (写真右)鳥葬の現場にあったお守り。西北ネパール学術探検隊がアチックミュージアムに寄贈、現在国立民族博物館に移管・所蔵されている<写真提供:高山龍三氏(元西北ネパール学術探検隊)> |
日本がちょうど戦後復興に浮かれ始めた頃だったこともあり、その時のことを後日談としてとある新聞上で敬三先生が書かれていました。「百里を行く者は九十を半ばとす」と。
「渋沢敬三」を動かしたのは何か?
──すこぶるご謙虚で、他利の精神に富まれた方だということがよく分りますね。
私財を投げ打ってまで、他人を支援したことをみても、なかなかできることではありません。
ところで、どうして敬三先生はそこまでされたのでしょうかね?
飯島 私見ですが、1番目にご自身が非常に学問がお好きであったということ、2番目に重圧の大きかった渋沢家に対して、何らかの思いが少なからずあったこと、3番目に急速な近代化によって失われつつあった日本の文化といったものを再度確認される作業だったのではないかと思っているんです。
──というと?
飯島 敬三先生は1896年、乳母にかしずかれ、人力車で幼稚園に通うようなご家庭に生れました。後に渋沢家から廃嫡されることになるお父様は敬三先生が小さな頃から家を留守がちで、寂しい思いをされたからでしょうか、幼少の頃から博物に著しい興味を抱くようになったようです。
 |
| 渋沢家4代。前列左から2番目が篤二氏(敬三父)、3番目が栄一氏、後列中央が敬三氏。栄一氏が抱えているのは敬三の息子雅英氏<写真提供:渋沢史料館> |
その一方で、出奔したお父様の代りに栄一氏の期待を当然のように一身に受けた敬三先生の重圧は、相当なものだったと想像できます。
早いうちから渋沢家の後継として育てられた敬三先生は、結局、実業の仕事に就かれ、ロンドンに赴任されました。その際もヨーロッパ各地の博物館などに接し、改めて民族学・民俗学博物館の必要性や民具の重要性を痛感されたそうです。
「富国強兵」のもと近代日本が失ったもの、つまり幕末維新の激動の時代を生き、近代日本の資本主義や工業の発展に尽力された敬三先生の祖父である渋沢栄一氏の世代が失わせてしまったものに対し、もともと興味があった学問の分野で「落ち穂拾い」をされようとしていたのではないかと思っているのです。
──なるほど。そういうことだったのかもしれませんね。
忘れたくない日本人の精神
──ところで、このような功績の大きい渋沢敬三という人物が、現代ではなかば忘れられているのはどうしてでしょうか?
飯島 おそらく敬三先生のされたご行為が、本当の「陰徳」、つまりひっそりと善行を積まれたからではないでしょうか。
こんなエピソードもあります。
時効かなとも思って何回かお話させていただいているものですが、ここでもご紹介させていただきたいと思います。
民族学会や民俗学会を中心に組織し、敬三先生が支援された「九学会連合」が、九州のとある離島に調査に行きました。中心に調査を行なった宮本常一先生が、島の方々へ調査協力のお礼として、後援者である敬三先生に、「島に電気がないところがあるので、電気をつけていただけないでしょうか」といわれたそうです。さすがに、これには敬三先生も絶句されたそうで…(笑)。
敬三先生に長いことお世話になって親交の深かった宮本先生も、さすがにいいすぎたかなと思われたそうですが、敬三先生は「ぼくの名前を出さないなら、やってみるよ」と、その場で手はずを整え始められたそうです。
──かっこいいですね。

飯島 本当にそうですね。
敬三先生へ尊敬の念を反芻すると同時に、現在では失われ掛けている敬三先生のような「陰徳の精神」の一端でも引き継いでいきたいものだとしみじみ思っています。
それにしても、渋沢家も、われわれ研究者も、そして日本も、敬三先生に甘えすぎたのではないかと悔やむように考えている昨今です。
──同感ですね。
飯島先生にこういったお話をお伺いできたお陰で、日本にこんな素晴らしい人がいたということを初めて知りました。
先生方のご尽力で、こうした偉大な方のご功績をもっと語り伝えていっていただけたらと思います。
本日はどうもありがとうございました。
 サイト内検索
サイト内検索