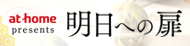こだわりアカデミー
青酸カリのような人工の毒より、自然界由来の毒の方が はるかに強いものがたくさんあるのです。
毒と薬は表裏一体。身近に存在する自然界の毒
日本薬科大学教授
船山 信次 氏
ふなやま しんじ

1951年仙台市生れ。75年東北大学薬学部卒。80年同大学大学院薬学研究科博士課程修了。薬剤師、薬学博士。イリノイ大学薬学部博士研究員、 北里研究所室長補佐、東北大学薬学部専任講師、青森大学工学部教授、弘前大学客員教授(兼任)などを経て、04年から現職。02年より Pharmaceutical Biology (USA) 副編集長。主な著書に「アルカロイド―毒と薬の宝庫」(共立出版)、「図解雑学 毒の科学」(ナツメ社)、「毒と薬の科学―毒から見た薬・薬から見た毒」(朝倉書店)、「毒と薬の世界史」(中公新書)など。現在、高等植物を中心に、その他、微生物由来の抗生物質など、天然物を起源とする有用な天然有機化合物の単離・精製、および化学構造の研究を行なっている。特に有用な物質が多い「アルカロイド」と称さ れる一群の天然有機化合物に着目する一方、「薬毒同源」の考えから、種々の植物由来の有毒成分を明らかにする研究も実施している。
2008年12月号掲載
実は身近に存在している「毒」
──先生は「薬学」の専門家でありながら、その延長で「毒」についてもご研究されていると伺っております。
食の安全が脅かされる事件が多発していることもあり、「毒」には暗いイメージが付きまとっていますが、先生は「毒」をどのようにお考えでしょうか。
船山 「毒」は”怖い””恐ろしい”といったイメージが強いかもしれませんが、実は非常に身近な存在です。
そもそも「毒」というのは、人間の都合で命名したに過ぎません。生体に何らかの作用を及ぼす化合物の中で、私達に芳しくない影響を与えるものを「毒」、都合の良い働きをする場合を「薬」と呼んでいるだけです。つまり、毒と薬は表裏一体で、これを私は「薬毒同源」と唱えています。
──「毒にも薬にもなる」というような表現には、そうした由来があるのですね。
毒にはどのような種類があるのですか。
船山 まず、自然界由来のものと、人工物に分けられます。植物、動物、微生物などの毒が自然界由来で、農薬や、サリンのような毒ガスなどが人工物に分類されます。
そして、自然界由来の「毒」の方が、圧倒的に種類が多く、一般に、毒性も強いのです。
 |
 |
| (写真上)スイセン”ティタ・テート”。スイセンはヒガンバナ科の植物。愛らしい姿をしながら、球根や葉に有毒アルカロイドを含む。葉をニラと間違えて食べ、食中毒を起こすケースも・・・ (写真下)アジサイの葉にも、フェブリフジン系のアルカロイドが含まれている<写真提供:船山信次氏> |
──それは意外ですね。ニュースなどで聞く「メタミドホス」に代表される人工的な毒の方が、「毒」の中心だと思っていました。
船山 例えば、「ボツリヌストキシン」という微生物の毒がありますが、これは1gで約5500万人もの命を危うくしてしまう程の威力があります。一方、有名な人工物の毒である青酸カリウムは、フグの毒の約1000分の1の毒性しかありません。
これ以外にも、強い毒性を持った自然の毒は数多くあります。
──それは驚きです。
 |
船山 また、自然界由来の毒は、多くが「アルカロイド」という化合物に分類されます。「アルカロイド」とは、窒素を含む有機化合物のうち、通常のアミノ酸や核酸などを除いた化合物をいうのです。
──ニコチンやトリカブトの毒が、確かアルカロイドですよね。
船山 その通りです。最近、スイセンの葉をニラと間違えて食べて中毒を起こしたり、料理の飾りとして置かれていたアジサイの葉を食べて中毒になる事件がありましたが、これらもアルカロイドのしわざです。
──確かに、毒は私達の非常に身近に存在しているんですね。
「毒」を持った生物が生存競争の中で有利だった!?
──そもそも、なぜ「毒」は存在するのでしょう。人間がつくり上げたものに毒があるのは理解できますが、自然のものである微生物や植物、昆虫、魚などが毒を持っているのは不思議な気がします。
「毒」も生物とともに進化をしているのでしょうか。
船山 「毒」そのものが進化しているとは思いません。今日までに、おそらく何億種類もの生物が自然淘汰の歴史の中で死に絶えてきたと考えられますが、その競争の中で、私達が「毒」と称しているものを持った生物が、持っていない生物より生き残るのに有利だっただけではないか・・・、と思います。
──結果的に「毒」を持つ生物が生き残ったというわけですね。
ところで、そもそも先生はなぜ「毒」に興味を持たれたのですか?
船山 実は、私は子どもの頃から植物が大好きで、中学生の頃は、お年寄りに混ざって園芸教室に通っていました(笑)。大学は植物学科にでも進学しようと考えたのですが、私が関わりたかった高等植物は詳しい分類も終ったと聞き、悩んでいたんです。
そんな折に、薬学部の生薬学教室で植物を研究している記事を見ました。また、ボタンやキク、アサガオは、初めは「薬」として日本に入ってきたと知り、不純な動機ではありましたが、薬学に興味が湧いたのです。
 |
| ヒガンバナは有名な有毒植物の一つ。秋の彼岸の頃になると、花茎だけを地面から伸ばして深紅の花をつける<写真提供:船山信次氏> |
──そして、現在は植物を中心とした「毒」のご研究をなさっているわけですね。結果的に、先生が志望していた道に進むことができたと。
船山 はい。ですから、仕事はほとんど趣味といっていいかもしれません(笑)。
天然物化学の研究では、日本は世界有数の先進国
──現在はどのようなご研究をしておられるのですか?
船山 主にアルカロイドです。先程申し上げた通り、アルカロイドは毒と薬の宝庫。少しでも役に立つものが発見できれば…と思い、さまざまな化合物の研究を続けています。
 |
| アサガオは薬用植物として日本に入ってきた。種子を下剤として使用していたが、作用が強すぎるため現在は使用されていない<写真提供:船山信次氏> |
──しかし、そうした化合物の化学構造式というのは、実際どのように調べるのですか。
船山 私は以前、北里研究所で「放線菌」を対象に抗生物質を探索する研究をしていましたので、それを例にご説明しましょう。
放線菌は土中にいて、1gの土から40種類くらい見付けることができます。そこで、この菌を別々に培養して、目的の菌株を選び出します。次いで、この菌を大量に培養して、目的成分を色々な分析手段を応用して精製し、純粋な形で活性成分(抗生物質の候補)を得ます。こうして得られた活性成分の化学構造を調べるのです。
そして、その方法は、主に化合物の紫外線、赤外線、核磁気共鳴、質量分析などの各種機器分析法による測定とその結果の解析で行ないます。おそらく、一般の方々の想像を絶する方法です。
──緻密な作業を求められる大変なご研究なのですね。
船山 でも、これが実に楽しいということが、薬学の道に進んで新たに分ったことです。
ちなみに、日本の天然物化学研究は世界でもトップクラスです。これは、万葉の時代から植物に親しんできた賜物かもしれません。
 |
| ジキタリスをはじめ、園芸植物には有毒なものが多い。なお、ジギタリスの葉には、心臓毒成分が含まれている<写真提供:船山信次氏> |
──確かに、北里柴三郎先生が破傷風菌の純粋培養に成功した他、志賀潔先生が赤痢菌を発見するなど、「薬」の研究分野において、日本人の活躍はめざましいものがあります。
船山 日本では古くから微生物の扱い方が上手だったことも、抗生物質研究における活躍の背景にあるのかもしれません。
1868年にフランスのパスツールが、ワイン等を低温で短時間処理し、有害な微生物の繁殖を抑える「パスツーリゼーション」という方法を考案しました。一方、日本では、「火落ち」と呼ばれた製品の劣化を防ぐ目的で、発酵の終わった日本酒に対して低温処理をする「火入れ」という方法を、実に室町時代から行なっているのです。これはパスツーリゼーションと同じ技術です。
──なるほど・・・。日本では日本酒の他にも、味噌や納豆、かつお節といった発酵食品が昔から身近に存在していましたから、おそらくその現象を観察してうまい対策を考えてきたのでしょうね。
船山 ええ。そして抗生物質の生産も、まさに微生物発酵の応用です。新しい抗生物質の発見や生産において、日本は世界の中でも有数な大国のひとつとなっています。
──それは素晴らしい! 日本にはこうした伝統もあったのですね。伺うところによると、先生も種々の新しい発見をなさっているとか・・・。先生をはじめ、多くの日本人が、今後も「薬」そして「毒」の研究でご活躍されることを願っています。
本日はありがとうございました。
 |
| 近々上梓予定の「毒と薬の世界史」(中公新書、書籍プレゼント参照)のゲラに手を入れる船山氏。「毒」と「薬」が人類の歩み(歴史)にどのように関わってきたのかについても興味を持ち、研究を続けている<写真提供:船山信次氏> |
 |
| 『毒と薬の世界史』(中公新書) |
船山信次先生が新著『<麻薬>のすべて』(講談社現代新書)を上梓されました。麻薬に関する基礎知識をはじめ、麻薬の歴史や人間との関わりなど、博物学的かつ正確な知識が紹介されています。また、『毒草・薬草事典』(サイエンス・アイ新書)も出版。人間の使い方次第で、毒にも薬にもなる植物ですが、同書では、国内で見られる代表的な毒草・薬草についてその奥深さが詳細に紹介されています。
 サイト内検索
サイト内検索