こだわりアカデミー
地球全表面の約67%を占める深海。 そこには数10万種以上の多様な生物が住んでいます。
深海底の奇妙な生き物
東京大学海洋研究所教授
太田 秀 氏
おおた すぐる
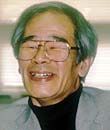
1944年新潟県生れ。 69年東京大学理学部生物学科卒業、71年同大学大学院理学系研究科動物学課程修了。東京大学海洋研究所助手を経て、現職に。著書に『海のはなし』(共著・84年、技報堂出版)、『海と地球環境』(共著・91年、東大出版会)、『海洋のしくみ』(共著・97年、日本実業出版社)など。
2000年6月号掲載
深海生物の多様な姿を手製のカメラで撮影
──深海は未知の世界で、先生のご研究は非常に楽しそうですね。そもそもなんでこの分野に…?
太田 私の研究の動機は 2つありまして、1つは先ほど話したような珍しい生物を見てみたいという欲求。もう一方は生物の生き様を見たい、生物の生態を見てみたいというものです。どちらかというと後者の生態学に重きを置いています。というのは、子供の頃から身近にいる生物が、どういう暮しをしているのかに強い興味を持っていたんです。生物は非常に多様性があり、あらゆる他の生物と関係し合って生きているじゃないですか。その様を見たいんです。その中でもなぜ深海かというのは、私が新潟県の佐渡島に生れ、海とともに育ってきたことが深く関係しているのかもしれませんね。
──しかし、海底にはそうそう簡単に行けるわけではない。大変な研究ですよね。
太田 そうですね。人間が行くのは困難ですから、カメラを深海に送り込み、だいたい海底 2,000平方mをカバーするように 2,000枚くらい写真を撮って調査します。ちなみに、そのカメラは私自身でつくったんです。他にもいろいろな計測器や潜水艇の設計などにも参画しているんですよ。
──ダビンチではないですが、いろんなことをなさるんですね。今後の研究も深海の生態を見ることを中心に進めていかれるのですか。
太田 そうですね。生物そのものを見て、その生き方などを調べ、多くの人に伝えていきたいと思っています。とかく学問は最前線の方に関心が行きます。例えば、今なら遺伝子研究といった分野にね。それはそれで重要なテーマですが、あまりに先端技術ばかりを追い求めると、素朴に地球を見て地球を考えるという古典的なサイエンスが途絶えてしまう。やはり地球という多様な生物が住む星で、人間を含むあらゆる生物が運命共同体として生きていくためには、最前線の学問だけではだめなんです。ですから私は、深海というフィールドにこだわりつつ、このような研究、学問を死守して次世代へ伝えていきたいと思います。
──私達人間はいろんな生物と関わり合って生きていますが、ともすると人間本位になりがちです。特に、われわれが普通では目にすることのできない深海の生物などは、身近にいないからということで関心も低くなりがちですが、地球全体の生態系を考えていく上では、決しておろそかにはできない部分だと思うんです。技術的には限界があって、ご研究はいろいろ困難もおありかと思いますが、どうか生命の謎を解き明かす意味でも、また古典的なサイエンスの精神を引き継いでいく意味でも、ますます先生には頑張っていただきたいと思います。
本日はありがとうございました。
 サイト内検索
サイト内検索




