こだわりアカデミー
人の食生活の原点「昆虫食」。 栄養価も高く、21世紀の食糧としても 期待が高まっています。
見直される「昆虫食」
東京農業大学応用生物科学部教授
三橋 淳 氏
みつはし じゅん
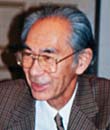
1932年、東京都生れ。55年東京大学農学部卒業。同年農林水産省農業技術研究所入所後、米国ボイストンプソン植物研究所へ留学。オーストラリア・CSIRO昆虫学研究所客員研究員を経て、84年、農林水産省林業試験場天敵微生物研究室長、88年、東京農工大学農学部教授。98年より東京農業大学応用生物科学部教授に。農学博士。日本応用動物昆虫学会賞、日本農学賞、読売農学賞を受賞。主な著書に『昆虫の細胞を育てる』(94年、サイエンスハウス)、『世界の食用昆虫』(84年、古今書院)、共編著に『虫を食べる人びと』(97年、平凡社)など。
2001年7月号掲載
これからの宇宙食は培養した昆虫の細胞?
──ところで先生は、昆虫食研究の他、昆虫の細胞培養も研究されているそうですね。
三橋 実は昆虫食研究はプライベートでやっている研究でして、大学では昆虫の細胞培養をしているんです。昆虫の体の組織から細胞を取り出し、バクテリアのように無限に増えるようにする研究です。
──動物の細胞培養には、限りがあったような気がしますが…。
三橋 おっしゃるように細胞がガン化しない限り、高等動物細胞の増殖は有限です。しかし、昆虫にはそのルールが当てはまらず、ガン化しなくても無限に増やすことができます。
最近、培養した昆虫細胞を使って薬をつくる技術などが産み出されており、注目されているんです。
──昆虫の新たな活用方法ですね。
最後に、細胞培養研究を含め、今後の研究テーマは?
三橋 先程いったように、排泄物やゴミを利用するなど、効率的に食用昆虫を育てる技術を確立させたいですね。
また、夢の一つなんですが、昆虫の細胞を大量に培養することで、動物タンパク質をつくり、食物とすることはできないかと考えているんです。しかし、今の段階では細胞1−sつくるのに、なんと数十万円もコストが掛ってしまう。安価で大量につくれる技術を研究したいですね。
そして先日、民間のアメリカ人が宇宙観光したように、これからは宇宙に行く機会が増えるでしょう。また宇宙ステーション計画もあります。そういうところで昆虫細胞の培養技術を使い、自給自足で動物タンパク性の食糧をつくれるまでにしたいですね。
──また、排泄物などで食用昆虫を大量に生産できるようになれば、エンドレスに循環させることができるかもしれません。非常に楽しみです。
三橋 そうですね。
さらには、最近体系化された「文化昆虫学」という新しい学問を盛り上げていきたいのです。この学問は、人の文化に関わる昆虫の研究全般をいいます。例えば、実学的な昆虫食研究はもちろんのこと、虫の声を鑑賞するとか形や色などを楽しむという遊び的な研究も含まれるんです。
──単に昆虫を生物学的にとらえるのではなく、その周辺のことを学問化するのですね。われわれにとっても身近で、興味深いテーマですね。成果を期待しております。
本日はありがとうございました。
![]()
トークちょっとこぼれ話
絶品!セミの幼虫の唐揚げ
これまで、いろんな昆虫を食べてきた三橋先生。一番美味しかった昆虫は「セミ」という。 セミは古代ギリシア時代に食べられていた記録があるほどで、日本でも長野県や山形県などで食べる風習が残っている。翅を取り除いて塩や醤油を付けて焼いたり、砂糖醤油で煮るなどいろいろな食べ方がある。 中でも先生は、「地中から這い出てきた成虫になる直前のセミの幼虫を唐揚げにしたものが絶品」とのこと。そのお味は…、「エビのような感じで、外はカリッと中はプリッとしています。機会があったらチャレンジしてみてください」と笑顔でおっしゃった。
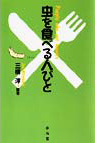 |
| 『虫を食べる人びと』(平凡社) |
 サイト内検索
サイト内検索




