こだわりアカデミー
自然と共存する第一歩は まず自分の家の庭を見直すことから。
動物と比べるとヒトがわかる
女子栄養大学人間・動物学研究室教授
小原 秀雄 氏
おばら ひでお
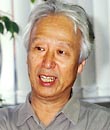
1927年東京生れ。国立科学博物館動物学部員を経て、現在、女子栄 養大学人間・動物学研究室教授。専攻は哺乳類学であるが、人間と動物との「共感」 関係など幅広い視点で研究を行っている。世界自然保護基金日本委員会理事、日本自 然保護協会理事長、国際自然保護連合保護委員会副委員長、トラフィック・ジャパン 委員長、日本環境会議代表理事、国際哺乳類学会委員(東アジア代表)などを兼任。 著書に、『日本野生動物記』『生物が1日1種消えていく』『動物たちの社会をよむ 』他多数
1992年10月号掲載
自然を理解する感性は子供時代に養われる
──なるほど、共存共栄の本能ですね。相手と自分の関係が本能的にわかり合える。人間も昔はその仲間にいたんでしょうね。それがいつ頃からか人間の方で勝手に隔てをつくってしまった。
小原 そうなんです。そこを私は言いたいわけです。例えば、われわれの世代が子供の頃は、まだヘビの卵を捕ってきて孵化させてみたり、トンボを採ってお腹を切ったり、というようなことを、親が汚いなどと行っても隠れてやっていた。
──今の子供は怖がってやりませんね。
小原 だいたい親がやらせない。汚いとか病気が移るとか言って自分たちも怖がっているんです。
──本来、子供は動物が好きなんですよね。動物園なんかに行くと柵にかじりついてみていますものね。
小原 小さいうちほどそうです。怖さを知りませんからね。そういう時期に動物や自然に触れないと感性が育たないんです。いきなり大人になってから動物は安全だ、可愛い可愛いなんて言っても絶対にだめです。
──理屈じゃないんですね。
小原 頭で理解して我慢したり無理して笑ってみたりしても、感性ではわかりません。
1998年3月に対談当時務めておられた女子栄養大学を定年退職。現在は同大学の名誉教授に。 また、野生生物保全物研究会会長、人間学研究所名誉所長、野生動物保護学会、ヒトと動物の関係学会、日本自然保護協会、国際自然保護連合保護委員会の顧問も務めるほか、自然の権利基金代表理事、アフリカゾウ国際保護基金理事(日本代表、募金団体)なども務めている。また数多くの受賞もされており、世界保護基金保護功労賞、国連環境計画(UNEP)のグローバル500賞などがある。 著書に『おもしろ自然・動物保護講座』『きみの体が地球環境』(全5巻)、『万物の死』。共著に『多様性と関係性の生態学』『ペット化する現代人』がある。
 サイト内検索
サイト内検索




