こだわりアカデミー
自然と共存する第一歩は まず自分の家の庭を見直すことから。
動物と比べるとヒトがわかる
女子栄養大学人間・動物学研究室教授
小原 秀雄 氏
おばら ひでお
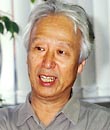
1927年東京生れ。国立科学博物館動物学部員を経て、現在、女子栄 養大学人間・動物学研究室教授。専攻は哺乳類学であるが、人間と動物との「共感」 関係など幅広い視点で研究を行っている。世界自然保護基金日本委員会理事、日本自 然保護協会理事長、国際自然保護連合保護委員会副委員長、トラフィック・ジャパン 委員長、日本環境会議代表理事、国際哺乳類学会委員(東アジア代表)などを兼任。 著書に、『日本野生動物記』『生物が1日1種消えていく』『動物たちの社会をよむ 』他多数
1992年10月号掲載
人間は自分で自分を飼っているようなもの
──今の環境問題もそういう意味で言葉だけで終っている感じですね。生態系とか食物連鎖など、学校で教わったり、新聞で見たりしてその意味は理解しているけれども、理屈だけでは何も生れないという感じがします。
小原 そういう意味でわれわれのすべきこととして、まず個々の家の庭から変えなくてはいけないと思います。環境問題をどうのこうの言いながら、自分の庭だけは虫もいないきれいな芝生にしておこうというのはおかしな話です。虫がいるのが本当なんです。といっても、モグラでも自分の巣の中からノミを追い出してきれいにしたがるんだから、ダイニングキッチンにまで動物を入れる必要は全くない。だけど庭にヒキガエルが出てきて卵を産んだりするのは当たり前なんですよ。ヒキガエルもいないような庭はどこかおかしいんじゃないかと思わなくてはいけないんです。イボがあっては汚いからどんどん捨てちゃえとか、大量発生などしようものなら、この池は汚いからと水を消毒したりする。そういうことまでする必要は本当ないはずです。それがどうしてああなっちゃうのか・・・。
──どんどん加速していってしまいそうな気がしますね。
小原 ますますね。何とかしないと自然と共存できなくなってしまう。子供たちの感性もだめになってしまいます。親が触らせない上、マンションの10階みたいなところに住んでいたのでは、よほど意図的にやらなければだめです。だから今後、都市の公園のつくり方というのはものすごく大きな問題になってきます。
──これからの都市計画のひとつの重要なテーマですね。
小原 人間はある意味で家畜に似ていると思いませんか。自分で自分を飼っている。囲いをつくってほかの動物から遠ざけ、社会システムで生産された食料を食べている。自己家畜化というやつです。これがあまりにも進んでいくとどうなるか・・・。
──恐ろしいですね。まず、自分の家の庭のあり方、そして自分の飼い方から考え直さなくては、本当に自然と共存する道というのは見出せないかもしれませんね。
本日はありがとうございました。
1998年3月に対談当時務めておられた女子栄養大学を定年退職。現在は同大学の名誉教授に。 また、野生生物保全物研究会会長、人間学研究所名誉所長、野生動物保護学会、ヒトと動物の関係学会、日本自然保護協会、国際自然保護連合保護委員会の顧問も務めるほか、自然の権利基金代表理事、アフリカゾウ国際保護基金理事(日本代表、募金団体)なども務めている。また数多くの受賞もされており、世界保護基金保護功労賞、国連環境計画(UNEP)のグローバル500賞などがある。 著書に『おもしろ自然・動物保護講座』『きみの体が地球環境』(全5巻)、『万物の死』。共著に『多様性と関係性の生態学』『ペット化する現代人』がある。
 サイト内検索
サイト内検索




