こだわりアカデミー
抗生物質の宝庫といわれる「放線菌」は、 驚きの新物質を生み出す可能性を秘めています。
身近な土壌に存在する「放線菌」
東京大学大学院農学生命科学研究科教授
大西 康夫 氏
おおにし やすお

1968年大阪府生まれ。91年東京大学農学部卒業、93年東京大学大学院農学系研究科修士課程修了。95年日本学術振興会特別研究員-DC(96年からPD)。96年東京大学大学院農学生命科学研究科博士過程修了、博士(農学)の学位取得、97年同研究科助手、2002年同研究科助教授、07年同研究科准教授、10年同研究科教授に就任、現在に至る。第10回(平成25年度)日本学術振興会賞受賞。
2015年4月号掲載
大西 土の中にいる放線菌は、周囲から栄養分を摂取して増殖しています。そのエリアに他の菌が介入してくると、当然ながら自分の栄養分が減ってしまうことになる。そこで、ある物質をつくり出し周囲に放出することで周りにいる菌を排除し(殺し)、自分の領地を確保しているというのが一般的な説です。
──その抗生物質が、われわれ人間社会では医薬として役立っているのですね。
大西 はい。放線菌に限らず、そうした物質は、その生物の生命活動に必須ではないということから、「二次代謝産物」と呼ばれていますが、人間は昔からこれらの二次代謝産物を薬や香料、染料などの生物資源として活用してきました。
スイッチをオンにすることで休眠遺伝子を呼び覚ます
──われわれに素晴らしい恩恵をもたらしてくれる抗生物質は、そのようにして放線菌が生み出しているんですね。先生の放線菌研究のテーマは?
 |
大西 放線菌の形態分化の制御や、二次代謝産物の生産の仕組みを解明することが主テーマです。
──これまでのご研究で、どのようなことが明らかになっているのですか?
大西 形態分化や二次代謝産物生産のマスタースイッチとなる制御遺伝子を、1999年にわれわれの研究チームが同定しています。その遺伝子産物が形態分化や二次代謝産物の生産に関わる多数の遺伝子のスイッチをオンにすることも明らかにしました。
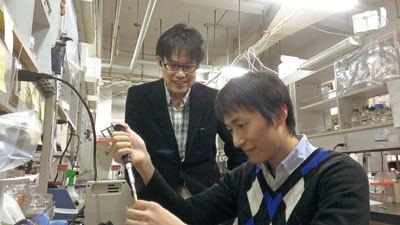 |
 |
| 醗酵学研究室のメンバーは26名。主に、抗生物質など有用な二次代謝産物をつくり出す仕組みや放線菌の形態分化の分子メカニズムについて研究を行っている〈写真提供:大西康夫氏〉 |
──そのことからどういう進展が?
 サイト内検索
サイト内検索




