こだわりアカデミー
美人とは、外見だけではなく 言葉遣い、立ち居振る舞い、教養が大切な要件です。
化粧の文化
化粧文化研究者 駒沢女子大学専任講師/資生堂ビューティーサイエンス研究所客員研究員
石田 かおり 氏
いしだ かおり

いしだ かおり 1964年、神奈川県生れ。92年、お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士課程修了。同年、資生堂に入社。ビューティーサイエンス研究所にて化粧文化の研究を開始。2000年、駒沢女子大学専任講師。学習院女子大学、日本女子大学、早稲田大学の非常勤講師も務めた。専門は哲学的化粧論・身体文化論。主な著書は『おしゃれの哲学』(95年、理想社)、『「裸のサル」は化粧好き』(99年、求龍堂)、「化粧せずには生きられない人間の歴史」(2000年、講談社)、『京の「はんなり」江戸は「粋」』(05年、祥伝社)など多数。
2005年11月号掲載
化粧とは、生きていく力
──先生は化粧文化を専門にご研究をされていると伺っております。
化粧は昔から、私達人間の生活に密接なものですが、学問の対象となったのは、意外にも最近のことだったようですね。
石田 そうなんです。化粧は、──ごまかす−∞−化ける−≠ニいうように、実態がないにもかかわらず、粉飾して、中身があるように見せる悪いイメージがあったせいか、長い間、学問の対象とはなりませんでした。
皮膚や毛髪、化粧品などに関する自然科学研究も、始まったのは1960年代からで、わずか50年程と、歴史の浅い分野です。
──先生は大学で哲学を専攻されていたそうですが、なぜ化粧文化について研究されるようになったのですか?

石田 縁があって化粧品会社の資生堂に就職したことがきっかけです。
哲学で学んだ、物の見方や考え方を活かし、世の中にどんな「美」を発信していけばいいのかなどを研究しています。
──改めて化粧の意義について伺いたいのですが、現代の人間にとって化粧の本質とは、一体何なのでしょうか?
石田 私のいう化粧とは、単に白粉や口紅をつけるというメーキャップに限られたものではありません。顔、体、髪を洗うこと、歯を磨くこと、ヒゲや爪の手入れも含みます。
──つまり、人間が自分の体に手を加えることすべてを、化粧として捉えているわけですね。
石田 そうです。化粧は社会生活を営む上で欠かせないものであり、自分が自分であるという、アイデンティティと深く関わっています。
──人間が化粧をするのは、『異性を惹き付けるため』だけではないのですね。
石田 そうです。
人はキレイになると自分に自信が持てるようになります。『キレイになる』というのは、実は人から評価される以前に、自分の思い込みに効いてくるのです。
自分に自信を持つと、人との接し方が変り、人間関係も変ります。それが明るい方向に循環していくと、人間関係がどんどん開けていくのです。
──これをメンタルケアや介護など、医療に応用したのが化粧療法なのですね。
石田 はい。高齢者や認知症患者、うつ病患者、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の方などは、自分で化粧をできるような環境にすると、症状が改善するのです。
精神的にまいり、自分を見失いそうになった時にも、化粧は大きな力を発揮します。
──化粧は心の傷をも癒す力がある…?
内面は外見に反映するといいますが、外見も内面を形成していく上で大切な要素なんですね。
石田 人は、化粧やヘアスタイル、服装など、個人を特定する要素が奪われると、自分が自分であることを保つことができなくなり、洗脳されやすくなってしまいます。
囚人や捕虜に同一の服装、髪型を強要することの意味もここにあります。
──人間のアイデンティティを保つ上でも、外見は重要な要素なのですね。
石田 自分がどういう行動をしたらふさわしいのか、自分づくりに大きな力を与えるのです。
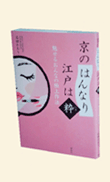 |
| 『京の「はんなり」江戸は「粋」』(祥伝社) |
2012年4月に駒沢女子大学人文学部人間関係学科教授に就任されました。
 サイト内検索
サイト内検索




