こだわりアカデミー
今も豊富に残る江戸時代の料理書。 「食」は「衣」や「住」に比べ 現代に通じるものが多いんです。
「江戸食」は日本古来の和食の原点
江戸食文化研究家 千葉大学名誉教授
松下 幸子 氏
まつした さちこ

1925年生れ。埼玉県さいたま市在住。47年、東京女子高等師範学校家政科卒業。埼玉師範学校、埼玉大学を経て、65年より千葉大学に在職し、教育学部助教授の後、同学部教授に。92年定年後より現職。そのほか大妻女子大学家政学部非常勤講師なども歴任。著書に『江戸料理読本』(82年、柴田書店)、『祝いの食文化』(91年、東京美術)、『図説江戸料理事典』(96年、柏書房)、共著に『再現江戸時代料理』(93年、小学館)、『料理いろは包丁』(94年、柴田書店)など多数。
2002年5月号掲載
飽食の時代だからこそ素食の原点「江戸食」に注目!
──先生は、江戸時代の料理書および食文化の研究で著名でいらっしゃいます。また合せて、歌舞伎や催し物にちなんだお弁当の企画でも活躍されていらっしゃるそうですね。本日は、その再現弁当をいただくことができる国立劇場第1食堂にお邪魔して、再現弁当のお話はもちろんのこと、江戸の食文化や現代と江戸時代との食の違いなどについてもお話を伺いたいと思います。
ところで、先日書店へ出掛けたところ、江戸時代の食に関する本を集めたコーナーがありました。今、随分と江戸の食文化が注目を集めているようですね?
松下 確かに最近、江戸時代の食文化に関心を持つ方が増えてきたようです。理由はさまざまあると思うのですが、私は、2つの理由を感じています。
まずは、健康志向の高まりですね。日本には、明治時代に洋食が入ってきたのですが、食文化は江戸時代とさほど変らなかったと思います。しかし戦後になると、急速に食文化が多様化し、それに伴って生活習慣病などが問題視されるようになってきています。そういう意味で、日本古来の質素な食事の基本である江戸食が注目を集めているのではないでしょうか。
──江戸時代の食事こそ真の素食だから、それに学ぼうというわけですね。
松下 それからもう1つは、懐古主義とでもいいましょうか…。現代は、生活全般が洋風化しており、日本本来の姿が失われつつあります。あまりにそれが進んだために、江戸時代のような日本らしさを懐かしんでいるのかなと。
──分るような気がします。着物も特別な時にしか着ませんし、住宅も随分変りました。今では畳のない家ですら、全然珍しくありません。
松下 衣食住の中で、食が一番手っ取り早く日本らしさを味わうことができ、ノスタルジアを感じることができるのかもしれません。
──ところで、先生が江戸時代の料理書や食文化の研究を始められたきっかけというと?
松下 もともと私は、調理学を専攻しておりました。調理学というのは、ジャガイモからビタミンを一番多く摂取できるゆで時間を研究するなど、主に栄養成分がテーマの化学ですから、巨視的な食文化とはかけ離れているのです。
そんな私が、江戸時代の料理書研究を始めるに至ったのは、1974年に川上行蔵先生が始められた「料理書原典研究会」の会員募集の新聞広告に興味を覚え、早速会員になったことが発端なのです。この集まりは、江戸時代初期の料理書「料理物語」などを読むというもので、とても面白い講義でした。
──川上先生というと、今回私が読ませていただいた先生のご著書「祝いの食文化」の序文を書かれていらっしゃる方ですね?
松下 ええ。その他にもさまざまな方々との出会いも重なって、私はこの研究にはまっていったわけです(笑)。
──ですが、一口に江戸時代といっても、その間約270年。研究するにもいろいろご苦労が多いと思うのですが。
松下 そう思われますか? ところが、実は、江戸時代全般にわたる約200種あまりの料理書が、現在も主な図書館に所蔵されているのです。料理書には手書きの写本と、出版された刊本とあり、どちらも現在では貴重書です。その他、食品事典ともいえる「本朝食鑑」、総合百科事典の「和漢三才図会」など、当時の食文化を知る上で大変貴重な書物、資料が大切に保管されていますから、研究材料には事欠きません。とはいえ、庶民の食生活を知るための資料が少ないのが残念ですね。
──それにしても当時の文字を読むのは大変ではないですか? さらに、そこから文脈や意味を理解するのは、随分と根気が必要ではないかと思いますが。
松下 自分でいうのもおかしいのですが、本当にそう思います(笑)。千葉大学にいた時は、江戸時代の料理書を活字に起こしてまとめるという取り組みを、年1冊のペースではありますが、16年もの間続けていたんですよ。

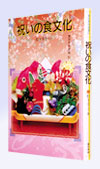 |
| 『祝いの食文化』(東京美術) |
 サイト内検索
サイト内検索




