こだわりアカデミー
今も豊富に残る江戸時代の料理書。 「食」は「衣」や「住」に比べ 現代に通じるものが多いんです。
「江戸食」は日本古来の和食の原点
江戸食文化研究家 千葉大学名誉教授
松下 幸子 氏
まつした さちこ

1925年生れ。埼玉県さいたま市在住。47年、東京女子高等師範学校家政科卒業。埼玉師範学校、埼玉大学を経て、65年より千葉大学に在職し、教育学部助教授の後、同学部教授に。92年定年後より現職。そのほか大妻女子大学家政学部非常勤講師なども歴任。著書に『江戸料理読本』(82年、柴田書店)、『祝いの食文化』(91年、東京美術)、『図説江戸料理事典』(96年、柏書房)、共著に『再現江戸時代料理』(93年、小学館)、『料理いろは包丁』(94年、柴田書店)など多数。
2002年5月号掲載
今も昔も、日本料理は目で食べるもの?
──さて、目の前にご用意いただきましたおいしそうなお弁当が、江戸料理を再現したお弁当ですね?
 |
| 2002年3月9日−24日に国立劇場で上演された歌舞伎の演目にちなみ、期間中、国立劇場第1食堂の特別メニューとなった「江戸の弥生弁当」。(左上から時計回りに)目鯛くるみみそつけ焼き、和えまぜ、煮物(里芋、椎茸、大根、蛸のやわらか煮)、ぎせい豆腐といったおかずに、ご飯、汁(カモ、セリ、ゆば)、キュウリのぬかみそ漬けが付いている |
松下 はい。現在、国立劇場で上演している演目にちなんで献立を立てました。
──3月は、『鉢の木』より「冬桜 二幕」と「秋の河童 一幕三場」でしたね。
松下 『鉢の木』の主人公の妻の名は、弥生といいます。そして3月は旧暦で「弥生」といいますよね。ですから「江戸の弥生弁当」と名付け、江戸時代の料理書の春の部から料理を選んで献立を決めました。
もちろん「秋の河童」にちなんだ料理も入れようと随分考えたのですが、河童自体が架空の生き物ですからなかなか難しく、結局、香の物をキュウリのぬかみそ漬けにしました(笑)。
──江戸時代の料理を再現する際に、気を付けていらっしゃることはありますか?
松下 彩りです。日本料理は目で食べるものといいますでしょ? もちろん、江戸時代の写真は残っていないのですが、錦絵などを見ると、当時も随分彩りに気を使っていることが分ります。また、料理書の中に記されている心得にも、彩りに気を配るようにとあるのです。
──味はどうなのでしょうか?
松下 再現する際には、江戸時代と同じ作り方で料理していますが、味は現代に合せています。というのも、江戸時代のまま再現したら、恐らく皆さん、塩辛くておいしく召し上がれないでしょう。江戸時代の人々は、電車や車なんてありませんから、とにかく歩く量が現在の人とは比較にならない程多かったわけで、必要な塩分量も、それだけ江戸時代の人の方が多かったのです。
──生活スタイル、運動量がまったく違いますからね。
それにしても毎回、演目にちなんだ献立を考えるのは大変ではないですか?
松下 ええ、特に毎回頭を悩ませるのは、予算との兼ね合いなんです…(笑)。
例えば、本日もう1つご用意した「明治の雛祭り膳」は、江戸東京博物館の企画展示にちなんで企画し、1030円でお出ししています。徳川家や大名家の雛祭りの献立も残っていますので、始めはそちらでとも思ったのですが、本膳形式ですから予算をオーバーしてしまいまして…(笑)。ですから、予算的にも比較的再現しやすい、明治時代の雛祭り弁当としたわけです。
 |
| 江戸東京博物館の企画展「こどもの世界−ひな・きもの・おもちゃ−」(2002年2月26日−4月7日開催)にちなみに献立を立てたという「明治の雛祭り膳」。期間中、館内の食堂「モア」のメニューとして人気を博した。小豆飯、しじみのみそ汁、かれいの煮付け、赤貝と大根のなます、盛り合わせ(小巻玉子焼き、赤白蒲鉾、小巻すし)に、雛あられが付いている |
──そんな裏話が、このお弁当にあったとは!(笑)とはいえ、実際に食べて歴史を感じられるなんて、とても素敵な取り組みです。今後もぜひ続けていっていただきたいと思います。
その他、今後の活動予定などは?
松下 現在、歌舞伎座のメールマガジンにおいて連載中の「江戸食文化紀行」に、さらに力を入れていくつもりです。
それから、まだ構想中なのですが、錦絵や再現料理の写真などを豊富に入れ、読みやすい文章と組み合せた、目で見ても読んでも楽しい本を出したいと思っています。もっともっと江戸の食文化に興味を持っていただきたいですからね!
──ご出版の日を心待ちにしております。
本日はありがとうございました。
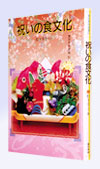 |
| 『祝いの食文化』(東京美術) |
 サイト内検索
サイト内検索




