こだわりアカデミー
環境考古学者にとって、 ゴミ捨て場やトイレは“宝の山”です。
ゴミ捨て場が宝の山。自然遺物から昔の生活を探る
(独)国立文化財機構 奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター 環境考古学研究室 室長
松井 章 氏
まつい あきら

1952年、大阪府生れ。専攻は環境考古学、動物考古学。71年、東北大学文学部入学後、78年〜79年まで米・ネブラスカ大学人類学科に留学。82年、東北大学大学院博士課程後期を中退し、現在の(独)国立文化財機構 奈良文化財研究所に就職。現在、同研究所 埋蔵文化財センター 環境考古学研究室 室長、京都大学大学院 人間・環境学研究科 文化遺産学分野 准教授を併任。著書に「環境考古学マニュアル」(編著、同成社)、「考古学と動物学」(共編、同成社)、「考古科学的研究法から見た木の文化・骨の文化」(編著、クバプロ)、「古代湖の考古学」(共編、クバプロ)など。
2008年1月号掲載
骨や植物などの「自然遺物」から昔の生活を探る
──先生は「環境考古学」の第一人者としてご活躍されていると伺っています。耳慣れない学問ですが、どういったご研究をされているのですか?
松井 もともと考古学は人間がつくったもの、つまり「人工物」の研究ですが、環境考古学は、人間がどういう環境の中で、どのような生活をしていたのかを研究する学問です。
──「生活」というと、具体的には、どのようなものが研究対象に?
松井 ゴミ捨て場やトイレの遺跡を発掘して出てくる遺物です。茶碗そのものよりも、その茶碗の中に何が入っていたのかを調べる、というと分りやすいでしょうか。
 |
| 中国浙江省にある田螺山遺跡にて、北京大学大学院の動物考古学専攻の学生に出土した動物骨の観察法を指導中。同遺跡は、約7000年前に稲作を行なっていた集落〈写真提供:松井 章氏〉 |
──茶碗の中身は残飯として捨てられるか、排泄物になる、というわけですね。こうした学問は昔からあったのでしょうか。
松井 1950年代に、イギリスのロンドン大学に「環境考古学部門」が設けられたのが最初です。それまで、出土した骨や植物は「自然遺物」と呼ばれ、考古学の対象外で、自然科学者に任すべきものとされていました。しかし、こうした遺物にこそ、過去の人々の生活情報が詰まっていることが気付かれ、注目され始めたのです。
日本で学問として確立したのは1970年代と、つい最近のことです。現在では環境問題や「トイレの考古学」が注目を浴びていることもあり、学問として発展してきています。
──なるほど…。
先生はなぜ、環境考古学にご興味を?
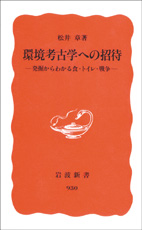 |
※松井 章先生は、2015年6月10日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)
 サイト内検索
サイト内検索




