こだわりアカデミー
本対談記事は、アットホーム(株)が全国の加盟不動産会社に向け発行している機関紙「at home time」に毎号掲載の同名コーナーの中から抜粋して公開しています。宇宙科学から遺伝子学、生物学、哲学、心理学、歴史学、文学、果ては環境問題 etc.まで、さまざまな学術分野の第一人者が語る最先端トピックや研究裏話あれこれ・・・。お忙しい毎日とは思いますが、たまにはお仕事・勉学を離れ、この「こだわりアカデミー」にお立ち寄り下さい。インタビュアーはアットホーム社長・松村文衞。1990年から毎月1回のペースでインタビューを続けています。
聞き手:アットホーム株式会社 代表取締役 松村文衞
和食の代表的な調味料「醤油」は、 日本の「国菌」である麹菌が生み出したのです。
「醤油」の美味しさの謎に迫る
東京農業大学短期大学部醸造学科教授
舘 博 氏
たち ひろし

1953年京都府生まれ。77年東京農業大学農学部醸造学科卒、同大学院農学研究科博士前期課程農芸化学専攻修了。同大助手、講師などを経て、2002年教授に。10年から短期大学部部長。同年「醤油功労賞」受賞。万能調味料の謎を解くため、研究一筋40年、自他ともに認める「醤油博士」。著書に『しょうゆの絵本』(農山漁村文化協会)、『しょうゆが香る郷土料理』(日本醤油協会)など。
2014年2月号掲載
日本の食文化が評価され、「和食」が無形文化遺産に!
──先日、ユネスコの「無形文化遺産」に「和食」が登録されました。海外ではすでに日本食ブームが起こっていますが、これを機にさらなるファンが増えることでしょう。
ところで先生は、その和食の調味料として代表的な「醤油」の研究を約40年間続けてこられ、「醤油博士」として有名でいらっしゃるそうですね。
舘 祖父の代から醤油の研究を続けており、農学界の「華麗なる一族」なんて呼ばれています(笑)。
──それはすごい!
しかし、われわれにとって醤油はとても身近な調味料なのに、これまで改めて考えることはありませんでした。ぜひこの機会に、醤油の基礎知識について教えていただけますか?
舘 醤油のルーツは「醤(ひしお)」と呼ばれるもので、中国から伝わってきました。醤とは、食塩を用いた保存食のことで、肉を用いると「肉醤(ししびしお)」、野菜を用いると「草醤(くさびしお)」、魚を用いると「魚醤(うおびしお)」に分類されます。狩猟民族だった原始人が、食塩により肉を保存できることに気が付き、最初に「肉醤」ができたとされています。
|
|
──醤油は、日本の伝統的な醸造調味料ですが、原点は中国だったんですね。
近著紹介
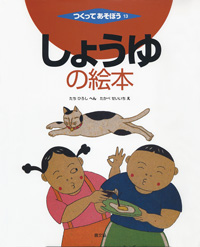 |
| 『しょうゆの絵本』(農山漁村文化協会) |
近況報告
舘 博先生は、2019年3月に退職されました。
 サイト内検索
サイト内検索
このサイトに掲載している情報の無断転載を禁止します。著作権はアットホーム株式会社またはその情報提供者に帰属します。
Copyright(C) At Home Co., Ltd.





