こだわりアカデミー
幕末から明治初期にかけた動乱の時代、 「出雲」は重要な役割を果たしたのです。
近代日本に影響を与えた「出雲」
明治学院大学国際学部教授
原 武史 氏
はら たけし

1962年東京都生れ。早稲田大学政治経済学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程中退。国立国会図書館職員、日本経済新聞社東京社会部記者、東京大学社会科学研究所助手などを経て、1997年山梨学院大学法学部助教授、2000年明治学院大学国際学部助教授、04年より現職。08年4月より同附属研究所所長も務める。専門は日本政治思想史。著書『「民都」大阪対「帝都」東京――思想としての関西私鉄』で、サントリー学芸賞社会・風俗部門、『大正天皇』で第55回毎日出版文化賞、『滝山コミューン一九七四』で第30回講談社ノンフィクション賞、『昭和天皇』で第12回司馬遼太郎賞などを受賞している。近著に『団地の時代』『沿線風景』『「鉄学」概論』など。
2011年2月号掲載
原 幕末から明治維新にかけて、実は〈出雲〉が思想史的に重要な役割を果たしたのです。
日本書紀の「国譲り」では、条件交渉がなされていた!?
──本題に入る前に、すこし整理させていただきたいのですが、「出雲」といえば、出雲大社の主宰神である「オオクニヌシ」を連想します。
そして、日本の国の興りについて伝える「古事記」や「日本書紀」の中では、オオクニヌシが、アマテラスの孫・ニニギに国土を譲り隠退した「国譲り」が伝えられていますね。
「古事記」や「日本書紀」では、伊勢神宮の祭神・アマテラスが最高神的な存在のように感じるのですが、「譲る」ということは、もともとはオオクニヌシが統治していた、ということですか?
原 「国譲り」については、日本書紀をきちんと読んでみると、大変興味深い発見があります。
正史と認められている日本書紀は、本文のほか、それに添えられる「一書」という形で、多くの異伝、異説が書き溜められているのですが、国譲りに関する限り、本文と異説部分である「一書第二」では、書かれている内容がずいぶん異なるんです。
──具体的には?
原 日本書紀の本文では、アマテラスの勅によって、オオクニヌシが国土を皇孫にすんなり譲っています。
しかし、「一書第二」では、オオクニヌシがアマテラスの使者から「あなたが行なわれる『顕露の事』はアマテラスの孫のニニギが治めるようにしましょう。その代わり、あなたは『神事』を治めてください」といわれており、オオクニヌシは「私が治めるこの世のことは、ニニギが治められるべきです。私は退いて『幽事』を担当しましょう」と返答した様子が描かれています。
 |
| オオクニヌシの子とされるタケミナカタと高天原から遣わされたタケミカヅチが力競べをしたという「国譲り」神話の舞台・稲佐の浜〈画像提供:(社)島根県観光連盟〉 |
──つまり、条件交渉というか、役割分担をしてお互いが譲りあったというわけですね。
私はオオクニヌシはニニギに国を譲って尻ごみするように隠退し、支配権を一切失ったように理解していました。
ちなみに、「顕露の事」、「幽事」とは何を指しているのでしょうか?
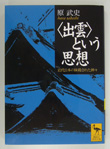 |
| 『<出雲>という思想』(講談社) |
 サイト内検索
サイト内検索




