こだわりアカデミー
幕末から明治初期にかけた動乱の時代、 「出雲」は重要な役割を果たしたのです。
近代日本に影響を与えた「出雲」
明治学院大学国際学部教授
原 武史 氏
はら たけし

1962年東京都生れ。早稲田大学政治経済学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程中退。国立国会図書館職員、日本経済新聞社東京社会部記者、東京大学社会科学研究所助手などを経て、1997年山梨学院大学法学部助教授、2000年明治学院大学国際学部助教授、04年より現職。08年4月より同附属研究所所長も務める。専門は日本政治思想史。著書『「民都」大阪対「帝都」東京――思想としての関西私鉄』で、サントリー学芸賞社会・風俗部門、『大正天皇』で第55回毎日出版文化賞、『滝山コミューン一九七四』で第30回講談社ノンフィクション賞、『昭和天皇』で第12回司馬遼太郎賞などを受賞している。近著に『団地の時代』『沿線風景』『「鉄学」概論』など。
2011年2月号掲載
原 平田篤胤は、「顕露の事」とはこの世(現世)での治政、「幽事」とは冥府(あの世)を治めることと解釈しています。
さらに、「顕」の治政者も、いずれは死んで「幽」の世界に行き、幽を治める者の支配下に入るのだから、「顕」に対して「幽」の方が優位であり、アマテラスよりオオクニヌシの方がえらいのだと主張しました。
──伊勢神宮の下に全国の神社を階層的に組織編制した国家神道とは違った解釈ですね。
原 そうなんです。この、オオクニヌシを中心とする篤胤独自の神学が投げ掛けた波紋は大きく、それがやがて明治初期に宗教論争を引き起こすことになったのです。
近代日本にも宗教論争があった!
──この近代に宗教論争があったんですか!? 驚きです。
原 1867年の大政奉還に続き、新政府は「祭政一致」を標榜し、古代の神祇官を再興する方針を出しました。つまり、神道の立場が急速に高まったわけです。
──そうすると、どの神を主宰神として祀るかで、争いが起きる・・・。
原 ええ、オオクニヌシを神道事務局の祭神に加えるべきか否かをめぐる祭神論争が起きました。
復古神道に基づいてオオクニヌシを合祀すべきだとする「出雲派」に対して、「伊勢派」は出雲派の主張を「国体」に反するものだとするなど、論争は混迷を極めました。
出雲派の中心となったのは、出雲大社の大宮司で、八十代国造を名乗る千家尊福でした。一方、伊勢派の中心となったのは、田中頼庸や浦田長民ら、伊勢神宮の神官達でした。
──しかし、先生が先程おっしゃった日本書紀の「一書第二」の部分を読むと、出雲派が有利ですね。
原 そうです。実際、純粋な神学論争として見れば、出雲派に有利な状況で展開されていきました。
そこで危機感を感じた伊勢派は、出雲派よりも権力に近かった立場を利用して、天皇の勅裁を仰ぐよう働き掛けたのです。
──そして、伊勢派が勝利し、第二次世界大戦終戦まで、国家神道として国家主義思想を支えたのですね・・・。
原 その通りです。神道は宗教でないとした国家神道が確立される背景には、祭神論争をきっかけとする〈出雲〉の抹殺があったと見ています。
──出雲の神々は今も人々の心のなかで脈々と生きていますが、近代において、出雲はいろいろな形で関わっていたわけですね。
 |
| 出雲大社は毎年、この海辺(稲佐の浜)で全国より参集する神々を迎える「神迎祭」を執り行なっている〈画像提供:出雲大社〉 |
今回は先生のお話を伺って、近代をまた別の角度から眺められるようになったような気がします。いろいろな視点から、物事を見ていく大事さを、改めて実感しました。
本日は、どうもありがとうございました。
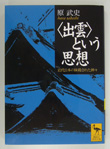 |
| 『<出雲>という思想』(講談社) |
 サイト内検索
サイト内検索




