こだわりアカデミー
私は世界でただ一人の「サイエンス・ナビゲーター」。 数学の面白さ、感動を、多くの人に伝えたい!
「数学大国日本」の未来を救う
東京工業大学世界文明センターフェロー
桜井 進 氏
さくらい すすむ

1968年山形県生れ。東京工業大学理学部数学科、同大大学院社会理工学研究科価値システム専攻卒業。在学中から塾講師として教壇に立ちながら、身近なものや数学者の人間ドラマを通して、数学の楽しさや美しさを伝える「サイエンスエンターテイメント」活動を展開。2000年より全国各地で数学のロマンをナビゲートしている。著書に、『雪月花の数学』(祥伝社)、『感動する!数学』(海竜社)、『天才たちが愛した美しい数式』『和算式計算ドリル』(ともにPHP研究所)、『江戸の数学教科書』(集英社)、『インド式計算暗算ドリル』(宝島社)、『数学のリアル』(東京書籍)、『数学で美人になる』(マガジンハウス)、『2112年9月3日、ドラえもんは本当に誕生する!』(ソフトバンククリエイティブ)など多数。
2010年12月号掲載
桜井 そもそも数学とは、文字通り「数の学問」ですが、私達にとってとても身近なものなんです。家や職場、普段乗っている電車の中にも数字がいたるところにありますし、皆さんが使っているコンピュータだって数学の論理で成り立っているのはご存じの通りです。実は数学は私達の生活の中にしっかりと浸透していて、とても役に立っているのです。
──確かに数学はとても身近で、私達にとってなくてはならないものですね。
音楽や芸術などと違い、数学は国境を越えて普遍
桜井 しかも、皆さん気付いていないかもしれませんが、実は私達は生来「数」というものが好きなんです。小さい子どもを見てください。数を覚えるようになると、ごく自然に周りのものの数を数えたり、同じものを足したりしていませんか。子どもの時はなんの抵抗もなく、むしろ面白がっています。「数を感じている」ともいえます。
──そういえば、どこの国でも数のオモチャがあったり、カード遊びがあったりしますね。
桜井 人間には生れながらに「視覚」「聴覚」「嗅覚」「触覚」「味覚」の「五感」というのがありますが、私は「数覚」というのもあるのではないかと思っている程です。それなのに、成長するに連れて数学が嫌いになっていくというのは、本当に残念です。
もっというと、数学は、音楽や芸術などと違い、国や民族、人種、宗教等により価値が変るということはない。例えば、2500年前にできたピタゴラスの定理(直角三角形の三辺の長さa、b、cの間に成り立つa2+b2=c2)は絶対的な真理であり、時を経ても朽ち果てることはないでしょう?
──ああ、確かに。数学だけは国境を越えて普遍ですね。素晴らしいなあ。
ところで、ちょっと話がそれますが、それ程に社会の役に立っている割には、数学で特許を取っているものってないですよね。
桜井 数学というのは、自然の定理を発見する学問であり、発見された定理は人類共有の財産です。つまり発見であり発明ではないので特許を与えることができないのです。
もっとも、そもそも数学者というのは、「真理」を発見・追求することを無上の喜びとするのであり、金儲けとかに捉われない、誇り高い気持ちを持っているともいえると思います。
──なるほど。先生のおっしゃる数学の面白さ、感動の原点が分ってきたような気がします。
桜井 ありがとうございます。
だから、少しでも多くの人達に数学を好きになってもらえるようにしたい。まずは、数を「感じ」てもらって、そこから「考える」ようになってもらいたい。それが私の「サイエンス・ナビゲーター」としての活動の目的です。
昔の数学者の苦労話に感動で涙を流す聴講者も
──先生のご講演では、具体的にどんなことを教えておられるのですか?
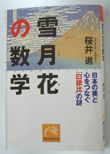 |
| 『雪月花』の数学(祥伝社) |
 サイト内検索
サイト内検索




