こだわりアカデミー
江戸時代の人達は、植物の利用の仕方だけでなく 植物との共生の仕方も知っていたのです。
江戸で生まれた植物学−本草学事始
東京大学総合研究博物館教授
大場 秀章 氏
おおば ひであき

1943年東京生れ。64年東京農業大学農学部卒業後、65年東北大学理学部助手、79年東京大学理学部助手、 81年同大学総合研究資料館助教授を経て現職に至る。88年には中国コンロン山脈での中国総合科学調査に日 本人として初めて参加した。著書に『秘境・崑崙を行く』(89年、岩波書店)、『森を読む』(91年、岩波 書店)、『植物学と植物画』(96年、八坂書房)、『植物は考える』(97年、河出書房新社)、『バラの誕生』(97年、中央公論社)、『江戸の植物学』(97年、東京大学出版会)などがある。
1998年10月号掲載
医学、薬学ともいえる江戸時代の植物学
──本日は、先生のご専門である江戸時代の植物学について、お話を伺いたいと思います。
この時代、植物学は「本草学(ほんぞうがく)」と呼ばれていたそうですが。
大場 そうなんです。しかし、現在の「植物学」とは少しニュアンスが違います。
本草学は、主に薬用の観点から、植物を中心に動物、鉱物など自然物を研究する学問です。当時の医療は、手術ではなく、もっぱら薬による治療が中心でした。薬の成分の多くは植物でしたので、「薬の本(もと)となる草」ということから「本草」と呼ばれたんです。そして、本草を研究する人を本草家といい、多くは医者でした。そういう意味から、江戸時代の植物学は、医学や薬学ともいえます。
──例えばお腹が痛い時、それに効くといわれている植物を煎じて飲んだりしていたわけですね。私が子供の頃くらいまでは、そういうことが日常生活の中に残っていました。
しかしなぜ、本草学が生れたのでしょうか。
大場 戦国時代までは、いきなり矢が飛んできたりして、明日のわが身はどうなるか分からないような状況でしたから、植物の研究や医療にはあまり関心がなかったといえます。その後、徳川家康が江戸幕府を開き、世の中も落ち着いて、「自分で養生すれば長生きもできる」ということが保証される時代になってくると、一人ひとり健康を気遣うゆとりが出てきたわけです。しかし、当時の日本には、残念ながら病気や治療についての文献、資料がなかったのです。それで当時つながりのあった中国で、江戸時代より少し前に、李時珍(りじちん)という人が著していた『本草綱目』という書物をもとに、日本での薬の研究がスタートしたというわけです。
ところが、今では信じられないようなことですが、当時の人達は、日本にある植物は全部『本草綱目』に載っていると思っていた。言い換えると、日本と中国の植物は同じものだと思っていたんです。しかも、この本には実にインチキな絵がたくさん描かれていたにもかかわらず、それを頼りに一生懸命研究していたんです。
──ということは、中国にしかない薬草を、日本中駆け回って探したりしていた…?
大場 そうなんです。その後、日本には『本草綱目』に載っていない植物があると気づいた人が、有名な貝原益軒(かいばらえきけん)です。
彼は晩年、黒田藩に仕え福岡に住むようになるまで、日本中さまざまなところを歩いて回ったんです。そして広い見聞をもとに『本草綱目』と照らし合せて、「日本には『本草綱目』に載っていない植物がある。また、この書自体完璧ではない」ということに気づいた。そして、『本草綱目』の一部を取り入れながらも、彼独自の調査結果をまとめ、日本版本草書『大和本草』を出したんです。
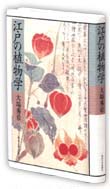 |
| 大場氏の著書『江戸の植物学』(東京大学出版会)は第32回造本装幀コンクール・日本書籍出版協会理事長賞を受賞した。 |
 サイト内検索
サイト内検索




