こだわりアカデミー
江戸時代の人達は、植物の利用の仕方だけでなく 植物との共生の仕方も知っていたのです。
江戸で生まれた植物学−本草学事始
東京大学総合研究博物館教授
大場 秀章 氏
おおば ひであき

1943年東京生れ。64年東京農業大学農学部卒業後、65年東北大学理学部助手、79年東京大学理学部助手、 81年同大学総合研究資料館助教授を経て現職に至る。88年には中国コンロン山脈での中国総合科学調査に日 本人として初めて参加した。著書に『秘境・崑崙を行く』(89年、岩波書店)、『森を読む』(91年、岩波 書店)、『植物学と植物画』(96年、八坂書房)、『植物は考える』(97年、河出書房新社)、『バラの誕生』(97年、中央公論社)、『江戸の植物学』(97年、東京大学出版会)などがある。
1998年10月号掲載
ヨーロッパにある植物の多くは日本から渡ったもの
──鎖国の中、出島でのオランダ貿易を通じて、海外の植物研究者も数多くやってきたそうですが。
大場 オランダ人を通じて、日本にはいろいろなきれいな植物があるとか、お茶のように植物を飲用しているなどさまざまな情報が、ヨーロッパに伝わったんです。それで、日本の植物に興味を持った研究者が大勢いました。しかし、日本に来るためには航海など危険が伴いますから、生半可な気持ちでは無理だったと思うんです。危険を乗り越えて最初に来た人が、ドイツ人のエンゲルベルト・ケンペルでした。
彼は、日本の植物を押し葉標本にして持ち帰っています。これは実物ですから、絵よりも情報量が多く、その後ケンペルはそれをもとに、日本の植物について本を書きました。その中には、植物の特徴だけではなく、柿とかツバキなどの有用植物を、日本人がどういうふうに使っているかについてまで書かれています。
その後、ヨーロッパの貴族や上流階級の人達の間で、ジャポニズムがブームになり、日本の美術工芸品を始めさまざまなものを収集する趣味が流行しました。もちろん植物も対象の一つで、そのためにいろんな植物がヨーロッパへ渡ったんです。
──ユリなんかも持ち出されたようですね。以前、「カサブランカ」は向こうのユリかと思っていたら、日本のヤマユリとカノコユリのかけ合せと知り、大変驚いたことがあったんです。
大場 当時は、ユリの球根1個が同じ重さの銀くらいの値段だったほど高級だったんです。
ユリ以外にも、ヤマブキやアオキ、サザンカ、ツバキ、それにツツジ類も大変人気がありました。これらは現在のヨーロッパでも、家の垣根や庭木に多く見られます。皆さん、ヨーロッパの庭は、いろいろな植物があってきれいだと思われるでしょうが、その中の多くの植物は日本から渡ったものなんです。

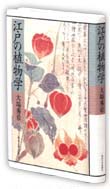 |
| 大場氏の著書『江戸の植物学』(東京大学出版会)は第32回造本装幀コンクール・日本書籍出版協会理事長賞を受賞した。 |
 サイト内検索
サイト内検索




