こだわりアカデミー
江戸時代の人達は、植物の利用の仕方だけでなく 植物との共生の仕方も知っていたのです。
江戸で生まれた植物学−本草学事始
東京大学総合研究博物館教授
大場 秀章 氏
おおば ひであき

1943年東京生れ。64年東京農業大学農学部卒業後、65年東北大学理学部助手、79年東京大学理学部助手、 81年同大学総合研究資料館助教授を経て現職に至る。88年には中国コンロン山脈での中国総合科学調査に日 本人として初めて参加した。著書に『秘境・崑崙を行く』(89年、岩波書店)、『森を読む』(91年、岩波 書店)、『植物学と植物画』(96年、八坂書房)、『植物は考える』(97年、河出書房新社)、『バラの誕生』(97年、中央公論社)、『江戸の植物学』(97年、東京大学出版会)などがある。
1998年10月号掲載
鎖国は個性的な本草家を生んだ
──旅をするのに相当な労力が必要だった江戸時代に、日本中の植物を調べた益軒は、非常に勉強熱心だったんですね。
大場 本草家は皆、とても熱心でした。もちろん、豊かな階層だった医者の中には、盆栽のような園芸的な分野に入れ込んだ人もいましたが、研究だけに没頭した本草家もたくさんいました。
いろいろな書物、文献などから、彼らが今のわれわれよりももっと強い探求心や好奇心を持って、研究に打ち込んでいた様子がうかがえます。
──江戸時代というのは、戦もなく、そうした勉強や研究に集中しやすい環境だったのかもしれませんね。
大場 そうなんです。しかも鎖国の時代だったから、あまりノイズに煩わされずに、自分の考えを貫き通しやすい、一つのことに集中しやすい環境ができたのです。鎖国は弊害ばかりが指摘されていますが、そういう意味でメリットも少しあったわけです。ですから、本草家も大まかな流派や学派はありましたが、みんな一人ひとり非常に個性的なんです。文献も単なるレポートや調査データというのではなく、自分の目で見たこと、確かめたことを、いきいきと伸びやかに書いており、それぞれの「人生物語」という感覚で読めて、ついつい引き込まれてしまいます。私は、彼らの生き方を見て、そこから江戸時代に関心を持ったんです。
──研究が人生の一部になっていて、その生き方が文章ににじみ出てくるんでしょうね。
また、文献の中には、図鑑のような精密な絵が描かれているものもあって、眺めているだけでも楽しいですね。先生の著書『江戸の植物学』の表紙にも、本草家の絵が使われていますが、聞くところによると装丁の賞を取られたとか。
大場 はい、おかげさまで。幕臣から本草家の道に入った岩崎灌園(かんえん)の絵なんですが、茎の太さなどで少し正確さに欠けてはいるものの、彼自身、とても優れた絵心の持ち主でした。
──先生の本には多くの本草家の絵が載っていますが、写真以上の伝達力があるように思いました。ただ見て描くのではなく、植物の特性をよく知っていて、見るポイントを心得ているんでしょうね。
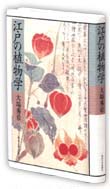 |
| 大場氏の著書『江戸の植物学』(東京大学出版会)は第32回造本装幀コンクール・日本書籍出版協会理事長賞を受賞した。 |
 サイト内検索
サイト内検索




