こだわりアカデミー
江戸時代の人達は、植物の利用の仕方だけでなく 植物との共生の仕方も知っていたのです。
江戸で生まれた植物学−本草学事始
東京大学総合研究博物館教授
大場 秀章 氏
おおば ひであき

1943年東京生れ。64年東京農業大学農学部卒業後、65年東北大学理学部助手、79年東京大学理学部助手、 81年同大学総合研究資料館助教授を経て現職に至る。88年には中国コンロン山脈での中国総合科学調査に日 本人として初めて参加した。著書に『秘境・崑崙を行く』(89年、岩波書店)、『森を読む』(91年、岩波 書店)、『植物学と植物画』(96年、八坂書房)、『植物は考える』(97年、河出書房新社)、『バラの誕生』(97年、中央公論社)、『江戸の植物学』(97年、東京大学出版会)などがある。
1998年10月号掲載
多様な植物に恵まれている国・日本
──そう考えますと、もともと日本は、たくさんの植物に恵まれている国なんですね。
大場 そうなんです。日本は島国で、しかも広大なユーラシア大陸の東に位置していますから、風が常に雨を運んできてくれます。その雨が植物には大変好都合で、植物が暮らすのにこんないいところはありませんね。
さらに、日本の国土は狭いですが、南北に長いため北と南では温度差があります。また、高い山や深い谷もあります。多様性に富んだ植物が育つんです。
──そういう恵まれた状況があったから、本草学のような植物利用の学問が根付いたともいえますね。
大場 日本人は本当に多くの植物を日常生活に取り込み、利用していましたね。しかし、無理な採取や利用は決してしませんでした。
──昔の人が植物を採取する時は、間引くようにして刈り取るなど、根絶やしにするようなことはしませんでしたね。
大場 森林にしても、人手が加わらないところ、たまに行って木や山菜などを採るところ、それから始終生活に使うところと完全に分けていました。江戸時代の人達は、植物の利用の仕方だけでなく、植物との共生の仕方も知っていたのです。
──最近、「環境共生」という言葉をよく耳にします。しかし、われわれはそれを理屈では分かっていますが、「では実際どうやって取り組んでいくのか」と聞かれると、具体的なノウハウは分からない。まさにそれを実行してきたのが、江戸時代の人々なんですね。
植物だけには限りませんが、「自然を大切にする」というのはただ「保護すればいい」とか「触らなければいい」ということではないと思うんです。手をかけてやらないといけない自然だってありますし、利用することでお互いが生き残っていけるものもあるわけですから、われわれはそれを見極めて、江戸時代よりも優れた植物との共生関係を築いていかなければいけませんね。
本日はありがとうございました。
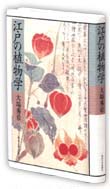 |
| 大場氏の著書『江戸の植物学』(東京大学出版会)は第32回造本装幀コンクール・日本書籍出版協会理事長賞を受賞した。 |
 サイト内検索
サイト内検索




