こだわりアカデミー
西洋と異なり、鯨を余すところなく完全利用する日本。 わが国の捕鯨文化は、現在も生き続けています。
世界に誇りたい日本の捕鯨文化
桜美林大学国際学部国際学科教授
高橋 順一 氏
たかはし じゅんいち

たかはし じゅんいち 1948年、千葉県生れ。京都大学文学部卒業、84年、ニューヨーク市立大学大学院修了。ブルックリン大学講師、文化女子大学講師などを経て、1989年桜美林大学国際学部助教授、のち教授。北米の原住民に関する文化人類学的・言語学的研究と共に、日本の捕鯨者および捕鯨コミュニティに関する多くの著作を発表。捕鯨者のアイデンティティーなどの問題を中心とする日本海洋文化の研究を行なっている。著書に「女たちの捕鯨物語」(日本捕鯨協会)、「鯨の日本文化誌」(淡交社)社)など。
2005年7月号掲載
鯨が食べる魚の量は世界の漁獲量の3〜5倍
──日本の調査捕鯨というのは、どのような役割を果たしているのでしょうか?
高橋 目視で頭数を数えるとともに、資源量やオス・メスの比、DNA調査による繁殖群の構成など、徹底した調査が行なわれていますが、これほど徹底した調査は世界でも日本しか行なっていません。
科学的調査の成果に対しては、国際社会から広範な支持が集まっているのです。
──よく鯨の数は増えていると聞きますが、実際のところはどうなのですか?
高橋 資源量は確実に回復しているようです。近年では、鯨が沿岸に近づいており、網ごと魚を食べてしまうというような漁業への被害も増えています。
──それは大変ですね。
高橋 鯨が食べる魚の量は、世界の漁獲量の3〜5倍ともいわれています。
鯨はいわば、人間の競争相手でもあるわけです。
──えっ、そんなに−! すると、このまま鯨の数が増えていけば、生態系のバランスが崩れる恐れがありますね。
高橋 その通りです。特にミンク鯨の数が急激に増えていて、成熟するまでに要する時間も短くなっていると指摘されています。
胃の中身を調べると、以前はプランクトンだけを食べると考えられていたのに、季節によってはサンマやサバまで食べていることが分ってきました。
──随分と適応能力があるんですね。
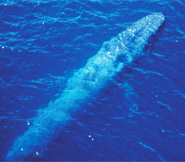 |
| 絶滅が危惧されているシロナガス鯨。世界で最も大きい動物で、体長は25−30m。主食は小さいオキアミ類<写真提供:(財)日本鯨類研究所> |
高橋 一方で、ミンク鯨と似た環境で生活するシロナガス鯨は、成育に時間を要する上に、餌を競合してしまい、なかなか増えず、回復に時間が掛かっています。
──鯨同士で競合もあるんですね。今後も漁業への被害など、多くの問題が発生しそうで心配です。
やはり、過剰に保護するのではなく、ある程度のコントロールが必要ですね。
 |
| 『日本伝統捕鯨地域サミット開催の記録』 |
 サイト内検索
サイト内検索




