こだわりアカデミー
嘘をつかないのが当たり前の「武士道」。 日本こそ、本当の意味での「契約社会」です。
日本人の心の根底にある「武士道」
国際日本文化研究センター教授
笠谷 和比古 氏
かさや かずひこ

1949年兵庫県生まれ。73年京都大学文学部史学科卒業、75年同大学院文学研究科修士課程修了、78年同大学院文学研究科博士課程単位取得退学。78年国立史料館(国文学研究資料館史料館)助手、文部教官。88年著書『主君「押込」の構造』(平凡社選書)でサントリー学芸賞を受賞。89年国際日本文化研究センター助教授、96年教授に就任し現在に至る。武士道研究の第一人者で、欧米型の個人主義・契約主義が蔓延する現代日本に警鐘を鳴らす歴史学者。著書は『武士道その名誉の掟』(教育出版)、『武士道と日本型能力主義』(新潮選書)など多数。
2015年2月号掲載
笠谷 それもありますが、もう一つ、「御家」のためという忠義もあります。江戸時代に入ると、主君への忠義よりむしろ御家や組織を守ることが重要と考えられるようになりました。それゆえ、主君の命令にどうしても納得がいかない、また主君が誤った行いをしていると思ったときには、自分の命をかけてでも主君を諌める、あるいは廃位に追い込む「押込(おしこめ)」という行為に及ぶことも実際にあったのです。一方、それに失敗すると、そのために餓死させられたり切腹を命じられた家臣もいます。
 |
──命をかけてまで組織を守るなんて・・・。当時の武士は、その強靭な精神力や心をどのように養っていたのでしょうか。
笠谷 その根本に「道(どう)」というものがあったのです。1642年、斎藤親盛という武士が著した武士の教訓書『可笑記』という文献は当時、武士だけでなく一般庶民の間でもベストセラーになりました。これにはまず、「嘘をつくな」「約束は守れ」という訓戒が最初に記されており、常に自らを律する教えを説いています。
──なるほど。それはすなわち、「うしろ指をさされない人間であれ」ということでもありますね。そういえば、契約社会と言われる欧米では、電話帳のようにぶ厚い契約書を交わしますが、日本ではペラペラの契約書で、ときには「口約束」で済ませられることもあります。これも、そうした武士道精神あればこそ、と言えますね。
笠谷 おっしゃる通りです。武士道精神は心の美学でもあるんです。私はその意味で、日本こそ本当の意味での契約社会と言えると思います。
 |
| 『武士道―侍社会の文化と倫理』(エヌティティ出版) |
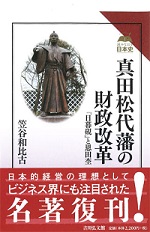 |
| 『真田松代藩の財政改革』(吉川弘文館) |
 サイト内検索
サイト内検索




