こだわりアカデミー
嘘をつかないのが当たり前の「武士道」。 日本こそ、本当の意味での「契約社会」です。
日本人の心の根底にある「武士道」
国際日本文化研究センター教授
笠谷 和比古 氏
かさや かずひこ

1949年兵庫県生まれ。73年京都大学文学部史学科卒業、75年同大学院文学研究科修士課程修了、78年同大学院文学研究科博士課程単位取得退学。78年国立史料館(国文学研究資料館史料館)助手、文部教官。88年著書『主君「押込」の構造』(平凡社選書)でサントリー学芸賞を受賞。89年国際日本文化研究センター助教授、96年教授に就任し現在に至る。武士道研究の第一人者で、欧米型の個人主義・契約主義が蔓延する現代日本に警鐘を鳴らす歴史学者。著書は『武士道その名誉の掟』(教育出版)、『武士道と日本型能力主義』(新潮選書)など多数。
2015年2月号掲載
外国人からみると、日本は特異で稀有な国
──ところで、先生はご著書の中で、日本は特異な国であり、外国からみると稀有な国である、そして、その背景には「武士道」があると書かれていますね。
笠谷 はい。まずは「明治維新」という大改革を成し遂げた国であり、欧米列強の軍門に下ることなく植民地化されなかった、アジアでは特異な国です。これらは、不屈の武士道精神があったからこそできたことです。
一方、東日本大震災のとき、暴動や略奪を起こすことなく、悲惨な状況にじっと耐え行儀良く並ぶ被災者の姿に、外国人は「稀有な国」だと評しました。海外では到底信じられない光景でしょうが、これも、日本人には自分を律することのできる武士道精神が宿っており、無意識のうちにそうした行動につながったのだと思います。
 |
| 東日本大震災発生後、雪の中、仙台市立茂庭台小学校で給水の順番を待つ人々。順番無視や略奪などなく、当たり前のように整然と列に並んで配給を待つ忍耐強さは、武士道精神が育んできた日本人の心の象徴か〈写真提供:河北新報社(2011年3月16日掲載)〉 |
──なるほど。私たちは普段、「武士道」を特別意識することも、学校や家庭で教えられることもありませんが、武士道精神は日本人の中に脈々と受け継がれているんですね。
笠谷 そうですね。もう一つ、海外でも驚きの目でみられた出来事があります。2013年7月、JR「南浦和」駅で、電車とホームの間に挟まれた女性を救出するため、乗客や駅員らが協力して車両を押したという行動です。
 |
| JR「南浦和」駅にて、電車とホームの間に挟まれた女性救出のため、車両を押して傾ける乗客や駅員ら。乗客が力を合わせて救助する姿に、「集団で英雄的な 行動を示した」「われわれだったら傍観のみ」など、世界から賞賛の声があがった〈写真提供:読売新聞社(2013年7月22日掲載)〉 |
──あぁ、覚えています。しかし、あの出来事のどこが? 困っている人を助けるのは、ごく当たり前のことだと思うのですが・・・。
 |
| 『武士道―侍社会の文化と倫理』(エヌティティ出版) |
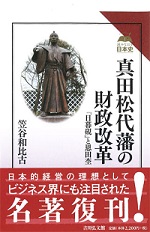 |
| 『真田松代藩の財政改革』(吉川弘文館) |
 サイト内検索
サイト内検索




