こだわりアカデミー
アマゾン川流域で発見された巨大古代遺跡からは 自然と調和した高度な文明社会がうかがえます。
ボリビア・アマゾンの古代文明
人類学者 立教大学社会学部教授
実松 克義 氏
さねまつ かつよし

さねまつ かつよし 1948年佐賀県生れ。70年日本大学文理学部卒業後、78年カンザス大学大学院修士課程修了。日本電気国際研修所講師、アテネフランセ講師を経て90年に立教大学講師に着任、現職に至る。シャーマニズムおよび古代文明の研究をライフワークとし、主に中米のマヤ、アンデス、アマゾン地域においてフィールドワークを行なう。専門は宗教人類学。主な著書に『マヤ文明 聖なる時間の書』(現代書林)、『マヤ文明 新たなる真実』『衝撃の古代アマゾン文明』(ともに講談社)、『アンデス・シャーマンとの対話』(現代書館)などがある。
2005年12月号掲載
アマゾンの古代文明発見で「人類大移動」のパラダイムは変る
実松 実は最近、アマゾンに古代遺跡が相次いで発見されていることもあって、「民族大移動」のパラダイムが変ってきているんです。もし、これまでの定説通り、人類がベーリング海峡を渡って、北米、南米と渡って来たのであれば、南米の遺跡より、北米の遺跡の方が古いはずなんです。しかし、実際は南米の方がおそろしく古い。一つのルートを通って人類が伝播したということではなく、もはや複数のルートで移動したということを考える必要があるでしょうね。日本ではまだのようですが、欧米ではこの考えがかなり浸透してきています。
──それにしても、この文明は非常に高度なすばらしい文化を持っているような気がするんですが…。
実松 はい、私もそう思っています。この文明の一番の特徴は、自然を排除するような都市的な方法で文明を築いたのではなく、自然を利用しながら、大改造計画を実施したことです。自然環境を人が住めるように変えながらも、環境と調和している。どのような方法で、この自然改造計画が行なわれ、どれくらいの成功を収めたのか、そこが知りたいと思っています。その方法が失敗であったか、成功であったのか、それは何ともいえませんが、そこを探ることに、現代的な意義があるとも思っています。

──学ぶべきところが随分とありそうですね。これだけの文明が相当な期間あったということは、失敗ではなく、成功であったとも思えなくもありません。
本日はありがとうございました。
 |
| 『衝撃の古代アマゾン文明』(講談社) |
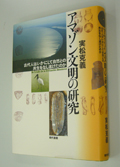 |
| 『アマゾン文明の研究ー古代人はいかにして自然との共生をなし遂げたのか』(現代書館) |
 サイト内検索
サイト内検索




