こだわりアカデミー
赤ワインに含まれるポリフェノールは 悪玉コレステロールの酸化を防ぎ、動脈硬化を予防します。
体に効く赤ワイン
お茶の水女子大学生活環境研究センター教授
近藤 和雄 氏
こんどう かずお

1949年東京生れ。79年東京慈恵会医科大学卒業後、メルボルンのベイカー医学研究所へ留学。東京慈恵会医科大学青戸病院助手、防衛医科大学校講師、国立健康・栄養研究所臨床栄養部室長を経て、現職に。医学博士。日本動脈硬化学会評議員。著書に『赤ワイン健康法』(95年、ごま書房、共著)、『からだに効く赤ワインの条件』(98年、講談社−写真−)、『中性脂肪を減らす食事』(2000年、成美堂出版、共著)など。
2001年2月号掲載
「悪玉コレステロール」は本当の『悪』ではなかった!!
──先生は、赤ワインに動脈硬化を抑制する効能があることを臨床的に証明され、権威あるイギリスの医学雑誌『ランセット』で紹介されるなど、その功績は世界的に評価されています。ここ数年、日本では赤ワインブームが続き、消費量も急激に増えたそうですが、なんと、ブームの火付け役になったのが、先生だったんですね。本日は、赤ワインはなぜ体にいいのか、その効能を始めいろいろお話を伺いたいと思います。
まず、動脈硬化とはどういう病気なのか、お教えください。
近藤 簡単にいうと、血管が厚く硬くなり、詰まってしまうことです。それが頭で起こると脳梗塞(こうそく)とか脳卒中、また心臓で起これば心筋梗塞と、まさに三大生活習慣病のうちの2つを引き起こす怖い病気なのです。
──その原因は何ですか?
近藤 いくつもありますが、中でもコレステロール、高血圧、たばこは、動脈硬化の三大因子と呼ばれています。特にコレステロールの増加は、一番の原因となっているんです。
──コレステロールが多いと、どうして動脈硬化になるのでしょう?
近藤 コレステロールと聞くと、皆さん「悪いもの」とお思いでしょうが、そうではありません。人間の身体は60兆個もの細胞から成っており、その骨格はコレステロールでできているほどで、身体にはとても必要なものなんです。コレステロールは脂質ですから、水溶性のリポタンパクという入れ物に取り込まれて各細胞まで運ばれるんですが、それには2つの種類がある…。
──よく聞く「善玉」、「悪玉」のことですね。
近藤 そうです。善玉コレステロール(HDL)は、体内の不要なコレステロールを回収するいわば掃除屋で、悪玉コレステロール(LDL)は細胞にコレステロールを供給する運び屋といえます。ただ、細胞にコレステロールが行き届き、LDLが過剰になると、それが動脈硬化のもとになるのです。
──健康維持のため、「悪玉のLDLを減らして、善玉のHDLを増やしましょう」なんていいますね。
近藤 よくいわれますね。ただ、単にLDLが直接的に血管を詰まらせるのではなく、活性酸素と結び付いて変化した酸化LDLが引き起こしているのです。
──単にLDLが存在するだけでは、動脈硬化は起きないと…。
近藤 そういうことです。活性酸素とは、体内でエネルギーをつくり出す時に必ず発生するもので、すぐに物質と結合しその物質を酸化させる、いわば腐らせてしまう有害なものです。
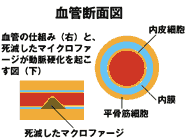 |
| 血管断面図 血管の仕組み(右)と、死滅したマイクロファージが動脈硬化を起こす図(下) |
LDLが過剰になると、細胞が必要とするまで体内をぐるぐる循環します。と同時に、LDLは血管壁の内膜(図参照)にも入り、内膜中で活性酸素と結び付いて酸化LDLへと変化するのです。酸化したLDLは身体には必要ないものですから異物となり、白血球の一種であるマクロファージが食べて処理してくれるのです。しかし、多くの酸化LDLがあると、マクロファージは際限なく食べてしまい、しまいには食べ過ぎで死滅してしまいます。その死骸が血管壁の中にたまっていって、壁を内側に盛り上げて、血管を詰まらせてしまうため、動脈硬化になるのです。
──LDLは「悪玉」と呼ばれていますが、本当の『悪』ではなく、酸化LDLが真の『悪』だったのですね。
 |
| 『からだに効く赤ワインの条件』(講談社) |
 サイト内検索
サイト内検索




